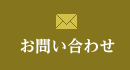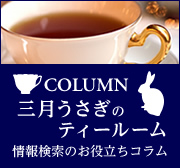情報検索コラム
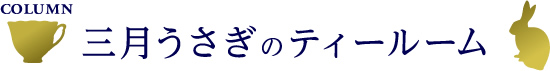
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -知識で終らない思考力と判断力-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
ここ1年半余りかけて書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてきました。書籍の執筆は得難いことを多く学ぶ経験となりました。いつかこの経験をコラムに書きたいと思っていたところ、一昨年あたりからフェイクニュースの拡散や、AIが自動で作成した記事の信頼性の問題などが広く取り上げられるようになったことをきっかけに、情報の信頼性判断を軸にして書籍執筆の経験を様々な方向から書いてみることにしました(コラムバックナンバー 一覧をご参照ください)。
1年半かけて情報の信頼性判断について様々に書いてきましたが、結局言いたいことはひとつだけです。このひとつを情報の信頼性判断のまとめとして、今回のコラムに書きたいと思います。
食品の消費期限の信頼性
商店街で乾物屋をやっている友人と雑談していたとき、食品の賞味期限や消費期限の話しになったことがありました。そのとき友人が言ったのです「食品を買っていきました。消費期限は過ぎていませんでした。でも傷んでました。食べたらお腹を壊しました。それで誰が悪いのかっていえば、そんなの食べたヤツがバカなんだよ」と。 この話しを聞いたときは “お腹を壊して苦しんでる人に、そんなキツイことは言わないであげてほしいなぁ” と思いましたが、フェイクニュースやAIの信頼性が世間で盛んに取り上げられるようになったとき、この友人の言葉を思い出しました。
食品の賞味期限や消費期限は、メーカーが責任を持って管理して記載してくれています。基本的には信じて良いとされます。でも製造過程での不測の事態や購入後の保存状況、また近年の気候変動などから期限前でも傷むことはあるはずで、最終的には自分で判断することになります。食品が傷んでいたなら、臭いがヘンだとか味がおかしいとか変色してるとか、「これは食べたらいけないな」と分かるための何かがあるはずで、それが分からなくて食べた、または分かっているのに期限表示を信じて食べてお腹を壊した。で、お店に苦情を持ち込まれたとして、皆さんがお店の人の立場ならどう思いますか。相手はお客さんなので表面的には「申し訳ありませんでした」と謝るとしても、その食品が傷んでいることを食べる前に分かってもらいたいものだと思うのではないでしょうか。乾物屋の彼の言葉「そんなの食べたヤツがバカ」は乱暴な言い方ですが、客観的に見れば最もかなと思います。
食品の期限表示は基本情報。それを自分の目の前にある食品に当てはめて、考えて判断して食べて良いかどうか決めるのは自分の責任。様々な情報の信頼性判断も同じだと思います。他人まかせににないで自分で考える。でも自分で責任を持って考えるひとは大変に少ない。このことを書籍執筆の課程でも、執筆後にも強く感じました。
知識を得て終わりにしない
この1年半のコラムでも何回か書いたとおり、本や雑誌、新聞記事やウェブ上で発信される情報は発信元の信頼性が高く、ウソは書いてなかったとしても虚構の世界です。本を書いた立場から言っても、本は分かりやすく説明するために分かりやすい例を挙げて説明します。だから本の知識は現実とはズレる。例えば英文法の本の場合、文法を説明するための例文を作るわけで、その英語をそのまま使う機会はほとんど無かったり(リンゴを指して Is this an apple? なんてマヌケな質問はめったにしないし)、実際の英会話ではもっと簡単な言い回しをしたりするし(Please give me some water. なんて言わなくても water please で通じてしまう)。
文法に限らず知識を学ぶ、または単にニュース記事を読むときも、それらは全てキレイに整理されて整えられた情報です。それを学ぶのは大事だけれど、学ぶのはゴールではなくてスタートです。知識は虚構の世界なので実際とは違う。知識を得たところから出発して自分で確認したり、考えたりするのが大事。このことはコラム251号「情報の信頼性判断のヒント -虚構(知識)をゴールにしない-」で詳しく書きましたが、書籍執筆中に出版社や原稿確認依頼先の先生から頂くコメントも、執筆後の講演やセミナーの受講者の皆さんから頂く質疑も、学んだ知識をそのまま言っているだけのかたが大多数です。
例えば「コスト削減」は良い、「格差社会」は悪い、「SDGsの推進」は良いなどなど。コレは良い、コレは悪い、と線で結んで正解を知って終り、という印象です。学校の試験問題は線で結んで正しい回答を書けばマルを貰えますが、それは教科書に書かれた虚構の知識が理解できたかどうかの試験にマルが貰えただけです。虚構と実際は違う。なのに虚構が正しいと思っているかたたちばかりで、誰もが例えば「コスト削減」は良いと同じことを言う。でもコスト削減で非正規雇用者が増加して格差が拡大したならどうなのか。
250号の「情報の信頼性判断のヒント -思考停止と信頼性判断の関係-」で、公共の特許情報室に勤務していたときの経験を書きました。時間外勤務の削減(良い)と、特許行政への協力(良い)が両立しなくて、それを所属組織の上層部からの命令で無理に両立させたために通常の情報室の運営に無理が生じて、特許行政への協力として特許検索のセミナーを行ったけど、実習無しの不十分なセミナーだったことを書きました。良いとされること(キレイな虚構)を行えば「良い」のではなくて、実際の状況のなかで本当はどうすべきなのかを考えなければいけないのに、何も考えずに良いとされることを行って自分を肯定する。私が所属していた組織の上層部は、このような思考回路でした。これを近年の流行り言葉の「思考停止」という用語で説明しました。良いとされることを何も検証せずにそのまま行うのは私は思考停止だと思いますが、一般的には良いとされることを行うのは思考停止とは言わない。例えば「SDGsの推進」は良いことなので、SDGsを推進しないのを思考停止とされます。だから思考停止しないで(実際には思考停止して)、SDGsの推進を行うのは良いとされます。
このような状況は、特定の考え方に染まっているとも言えて、例えば「ジェンダー平等」が「良い」とされた場合、新聞の論調もジェンダー平等が良いという前提で書かれる。だからどの記事も同じ思想で書かれる。これは実際にはフィルターバブル(コラム249号参照)の一種だと私は思っています。そして大勢のひとが良いと言っていることを自分も良いと言うことで、自分を肯定できて安心する。そんな構図が見えてきます。
念のため書いておくと、私はSDGsの推進は基本的には必要だと思うし、ジェンダー不平等は解決していったほうが良いと思います。でもどんな考え方にも良い面とそうではない面があるわけで、SDGsも特許情報から見ると、そんなにキレイに整理できる問題ではないと感じます。
何を信じればよいのか、ではなくて
フェイクニュースや、生成AIの信頼性の問題などが取り上げられると何を信じたら良いのかという話しになるのですが、ここで最初の話しに戻ってみましょうか。
食品の消費期限は基本的には信用できるけど、実際には状況によって傷んでいることもある。ときには悪戯などで期限の日付シールが貼り替えられていたりするかもしれない。ということは、自分で判断するしかない。情報の信頼性判断の判断力を鍛えるには思考力が必要で、知識を得ても、それで終わりにしないトレーニングが必要だと思います。そのためのヒントを長々と一年半かけて書いてきたつもりです。食品の判断で言えば最初に書いたように、臭いがヘンだとか味がおかしいとか変色してるとか、これらが判断のための知識としてのヒントです。これらのヒントをもとに自分の判断力をつけて頂ければと思いつつ書きました。ただし判断力をつけるためには思考力が必要です。
というわけで何を信じれば良いのかというならば、自分を信じる。消費期限の日付ではなくて、自分の判断力に責任を持つしかないと思います。で、自分の判断を信じて傷んだ食品を食べてお腹を壊したなら自分の判断が間違っていた(バカだった)。でも自分で判断したなら、どこに判断の間違いがあったかが分かる。だから同じバカ(言葉が悪くてすみません)でも、消費期限の日付を信じたバカとは違う。そこが大事だと思うのです。
「コミュニケーション」とか「労働環境」とか「成長戦略」とか、どこかから借りてきたカッコイイ知ったかぶりの言葉で語られる話しは知識をそのまま話しているだけで、何も考えていない話しなので正直に言ってつまらない。アナタから聞かなくても他の誰かから聞けば十分です、と思ってしまう。知識を語るのではなくて、思考を語る。そんな話しを聞きたいと私は思っています。
参考:情報の信頼性判断のヒント 一覧
第260号(2025/01/14)情報の信頼性判断のヒント -知ったかぶりの言葉の信頼性-
第259号(2024/12/10)情報の信頼性判断のヒント -サーチャーと情報と信頼性-
第258号(2024/11/12)情報の信頼性判断のヒント -書籍全文検索の利点、不利点-
第257号(2024/10/08)情報の信頼性判断のヒント -情報のコストから考える信頼性-
第256号(2024/09/10)情報の信頼性判断のヒント -情報の鮮度を判断するスキル-
第255号(2024/08/06)情報の信頼性判断のヒント -著作権を守る情報発信のために-
第254号(2024/07/09)情報の信頼性判断のヒント -質問して情報入手するスキル-
第253号(2024/06/11)情報の信頼性判断のヒント -バイアスによるミスリード-
第252号(2024/05/14)情報の信頼性判断のヒント -理由や根拠を上手に説明する-
第251号(2024/04/09)情報の信頼性判断のヒント -虚構(知識)をゴールにしない-
第250号(2024/03/12)情報の信頼性判断のヒント -思考停止と信頼性判断の関係-
第249号(2024/02/13)情報の信頼性判断のヒント -信頼性判断のヨコ軸とタテ軸(2)-
第248号(2024/01/16)情報の信頼性判断のヒント -信頼性判断のヨコ軸とタテ軸(1)-
第247号(2023/12/12)情報の信頼性判断のヒント -見えないものを見る目を持つ-
第246号(2023/11/14)情報の信頼性判断のヒント -情報検証の尻尾!を捕まえる-
第245号(2023/10/10)情報の信頼性判断のヒント -大規模言語モデルを使う-
第244号(2023/09/12)情報の信頼性判断のヒント -情報が関連しあう利点・問題点-
第243号(2023/08/08)情報の信頼性判断のヒント -他人の判断よりも自分の判断を-
第242号(2023/07/11)情報の信頼性判断のヒント -信頼性判断のための知識と思考-
第241号(2023/06/13)情報の信頼性判断のヒント -著者・出版社・校閲・査読-
コラム259号で、図書館司書もサーチャーも情報と人を結ぶ仕事という面で一貫していると書きました。私が最初に図書館司書を目指したのは、世の中の様々な考え方をいろんなかたに案内したかったのが理由だと書きましたが、もしも今もこの志しのまま司書を続けていたなら、たぶん挫折していると思います。なぜなら多くのかたは世の中の様々な考え方を知りたいなんて思っていないようなので。先生が言うことを理解して、テストでマルが貰えれば良しで、それとは違う考え方を知りたいと思う方は少ないようなのです。だから正直なところ特許情報や技術情報とユーザーを結ぶサーチャーに、仕事を移行できたのは良かったかなと思っています。特許情報や技術情報はユーザーやクライアントが思いつかなかった情報や、見つけられなかった情報を提供できると喜んで貰えるので。このコラムを書きながら、そんなことも思いました。