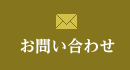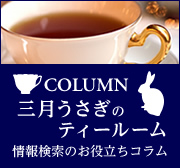情報検索コラム
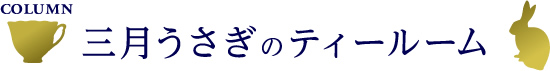
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -著作権を守る情報発信のために-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回のコラムも書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてみたいと思います。
生成AIが身近になった現在、生成AIと著作権の関連や問題点なども取り上げられるようになってきました。生成AIに限らず、様々な情報発信では著作権を守る必要があります。著作権については専門家のかたが様々に説明や解説をしています。私自身は単にサーチャーとして書籍を書いた著作者であり著作権法の専門家ではありません。つまり書籍執筆を含めた様々な情報発信において、一般的には著作権法に詳しくないひとが情報を発信するわけです。というわけで今回は書籍執筆に関連する著作権処理について書いてみます。皆さんが情報発信するとき、また情報入手するとき、そして生成AIと著作権の関連を考えるときの参考になればと思います。
著作権処理の判断は簡単ではない
私は図書館司書とサーチャー、ふたつの資格を持っています。サーチャーとしては特許調査が専門です。私の仕事に関係する「図書館」「データベース」「特許」は全て著作権法に関連する分野です。だから学生のときの司書課程に始まって、現在も常に著作権法を様々に学び、そして接しながら仕事しています。
例えば図書館関連の雑誌やサーチャー向けの機関誌などには著作権法の解説などが様々に掲載されるし、公共の情報室に勤務していたときは著作権法のセミナーにも参加しました。図書館と著作権法との関連の基本は著作権法第三十一条「図書館等における複製等」に始まって多くの条文が関連します。またデータベースと著作権法の基本は、著作権法第十二条の二「データベースの著作物」の項です。また知的財産基本法第二条2で「知的財産権」として「特許権、実用新案権」とともに「著作権」が記載されていて、特許は知的財産権としては著作権と同じ分野に入ります。特許法の本を読むと著作権と関連付けながら説明されることが多々あります。
というわけで常に著作権法に接しながら仕事をしてきているのですが、それでも上に書いたとおり「著作権法の専門家ではありません」です。むしろ仕事に関連して著作権法を学べば学ぶほど、著作権法の理解は簡単ではないと実感します。
インターネットで誰もが情報発信できる現在、情報発信するときは著作権法に注意する必要があるわけですが、発信者自身で正しく著作権処理の判断をするのは難しいと思います。著作権法にやや近い位置にいる(かもしれない?)私でも、著作権の理解や判断は難しいなかで、著作権法に普段から接しないかたにはさらに難しいだろうなと思います。
というわけで書籍執筆のときに著作権に関連して経験した様々なことを、お伝えしたいと思います。
出版契約書:著作者と著作権と出版権
本を執筆した、その著作物の著作権は基本的に著者にあります。著作者については著作権法第二条二項に「著作者 著作物を創作する者をいう」とされ、著作権者については文化庁のウェブページでは次のとおり説明されています。「著作権を有する者のことをいいます。一般に著作者が著作権者であることが多いです(以下省略)」
※参照URL https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/comment/list_ta.html
そして執筆した原稿を出版するためには、著作権者が出版社と出版契約書を締結します。私の場合は「出版権設定契約」を締結しました。出版権設定契約とは著作権者が「特定の者(味岡注:出版社など)に対し出版権を設定するもので、出版権の設定を受けた出版権者は設定行為に従って著作物を複製して頒布することができる」(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』著作権)と説明されています。
他の著作物への権利侵害
この出版契約書には出版する著作物(本)が、他の著作物に対して権利侵害しないことを保障する趣旨の条文が含まれます。例として日本出版協会の出版権設定契約ヒナ型(PDF)では次のとおり書かれています。
第15条(内容についての保証)
(1) 甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないこと、および本著作物につき第三者に対して出版権、質権を設定していないことを保証する。
(2) 本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。
※参考URL https://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/hinagata2015-1.pdf
甲が著作者、乙が出版社です。(1)に書かれているとおり「本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しない」ことを甲、つまり著作者が保証するということです。私が締結した契約書でも同じ趣旨のことが書かれています。
他の著作物の著作権を侵害するなと言われても・・・
上に書いたとおり甲、つまり著作者は他の著作物の著作権を侵害しないことを保証しなければいけない。しかしながら著作者は著作権法に詳しいわけではないのです。だから著作権処理の要不要の判断も正確にできないし、著作権処理の手順や方法も知らないのが普通です。
だから書籍執筆にあたって私は "出版社には著作権処理のための案内とか手引きとか、著作権処理の要不要判断のガイドラインのようなものがあるのだろうな" と勝手に推測していました。さらに編集者のかたが原稿を読んで著作権処理がなされているかどうかのチェックなどもするのだろうと思っていました。さらに言うと、出版契約は原稿が出来上がってから最終段階で初めて見ました。原稿執筆時は、他の著作物の著作権を侵害しない責任を著者(私)が負うものだということも知りませんでした。だから出版物に対しての著作権処理は出版社の法務部などがが行うのではないかとも思っていました。
特に私の著書の場合、検索例に用いる検索画面は全て検索システム側の著作物だし、表示されるデータも同様です。これらは単純な引用ではありません。これらの著作権処理の方法もさることながら、例えば著作権法に基づいて正しく引用する場合の書き方や引用元の記載方法など、出版社から何かしらの案内があると思っていたのですが、全く何もありませんでした。
私から出版社の編集者へ "執筆と出版における著作権処理の判断も方法も著者は詳しく知らないから、どのようにすれば良いかご教示ください" という内容の問合せメールを送ったのですが、全く無回答でした。せめて「他人の著作権を侵害しないことを保証するのは著者です」という回答でもよかったのですが、その回答さえ無くて、催促しても無回答。
著作権処理:どのように行ったか
しかたがないので著作権処理については、文化庁や著作権情報センターなどの信頼できる機関のウェブページを参照しながら処理しました。でも私の場合は上に書いたとおり、検索システムの検索画面やデータなど、単純な利用ではないので、これらは作成した原稿を各システム側へ送って確認と承諾をもらいました。これらの記録は今も残してありますが、各機関によって対応は様々に違いました。
例えば国立国会図書館は著作物転載の許可願いを提出する必要がありましたが、この許可願いは著者が行うものではなく、発行者(出版社)が公印を押して国会図書館へ提出するものでした。国立情報学研究所は送付した原稿の受領と内容確認のメールをもって「承諾」であり、書類等の提出は不要でした。国立情報学研究所は「画像転載許可」のメールをくださったうえで検索内容のチェックなどもしてくださって、とても丁寧な対応でした。科学技術振興機構(JST)も最終原稿の提出で「許諾」でした。日経テレコンは印刷部数と単価を事前に日経テレコン側へ知らせたうえで、申請書に出版社の公印を押して、掲載見本PDFとともに日経テレコンの担当者へ送る必要がありました。これも著者が行うものではなく、発行者(出版社)が提出するものでした。
とうわけで国立国会図書館や日経テレコンは出版社の公印を押した書類が必要など、著者だけ対応できるものではなかったです。
そのほかの引用や参考文献の記載なども慎重に判断して行いました。少しでも参考にしたなら「主な参考文献・参考URL一覧」に列挙するようにしました。また書籍から引用した場合はその書籍の出版社へ、正しく引用したことの報告として出来上がった本『社会人・学生のための情報検索入門』をお送りしました。これは著作権法の遵守としては行う必要はないのですが、以前、公共の情報室に勤務していたとき、セミナーに使う資料に他の本から引用したことがあって、この引用について著作権情報センターに確認したところ「法的には問題ないが、著者のかたが後で知って気を悪くされることのないように ”このように引用しました” という報告のために資料の現物を送ったほうが良い」とのアドバイスをもらった経験によるものです。
書籍をお送りしたのは全部で8社です(いずれも当時の名称)。新潮社(『図書館を使い倒す! : ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」』著者:千野信浩氏)、学習研究社(『がんばれヘンリーくん』訳者:松岡享子氏)、日外アソシエーツ、日本能率協会MDB、金融財政事情研究会、総合研究開発機構、専門図書館協議会、PATOLIS です。
ちなみに学習研究社に本をお送りしたところ、学研の担当者から「訳者の松岡先生が気を悪くされるといけないので、松岡先生へ直接送ってください」とのメールが届きました。そこで改めて松岡享子先生(当時、東京子ども図書館理事長)あてに挨拶と報告を記載した文書とともに本をお送りしました。そしたら松岡先生から「拝読しました」という直筆のお手紙が届きました。心温まる内容のお手紙で、本に引用されたことでヘンリーくんが自慢に思っているのではないかと書いてくださいました。さらに情報検索については松岡先生は図書館の先輩なのでパンチカード(!)のことも書いてくださって、感激しました。このお手紙は私の宝物です。松岡先生が2022年に亡くなられたときは、とても悲しかったです。松岡先生を好きだったかたは多いだろうなと思います。
印刷時の著作権対応など
その他にも著作権に関連したことは様々にあります。
例えば拙著 p.57の図7-1 の架空の新聞記事例と p.59の図7-3 架空のウェブページ例の中に、それぞれエアロビクス用シューズのイラストが入っています。このイラストは原稿作成時は仮のイラストとしてホームページ作成ソフトのイラスト集にあったスポーツシューズの絵を入れてありました。そして印刷時への注意として「このイラストはホームページ作成用のイラストだから著作権法上、書籍には使えないので別途出版用のオリジナルのイラスト(例えば印刷会社のイラストレータが作成するイラスト)に差し替えてください」と指示を入れました。
ところが最初の校正刷りが刷り上がってきたところ、指示が守られていなくて仮のイラストのままでした。校正では赤ペンとマーカーで絶対に見落とさないようにくっきりと「このイラストは著作権法上使えません。オリジナルのイラストに差し替えてください」と指示をだしました。そしたら第二校では直っていました。このような点も含めて残念ながら著作権をあまり気にしていない印象でした。
ついでに書くと、私の原稿は検索例画面と検索の説明が、なるべく同じページまたは見開きで見ることができるように作りました。例えば左ページの検索例の説明が、見開きの右ページに書いてあるようにしました。だから「このページと、このページは見開きで見れるようにしてください」という指示を複数箇所に入れたのですが、最初の校正刷りでは全く守られていませんでした。だから校正のときは同じ指示を再度、今度は絶対に守ってもらうように、くっきりと赤の太いペンで入れました。ここまで指示しないとやってもらえないものかと思いました。他にも下線の位置や太字の指示なども守られていなくて、初校は真っ赤に直しました。
出版社の著作権対応
今まで書いたことを簡単にまとめると次のとおりです。
(1)著作物(本)の出版権は出版者(出版社)にある。
(2)しかし、出版する著作物(本)が他の著作物に対して権利侵害しないことは著者が保証する。
(3)ただし、著作権に詳しくない著者に対し、著作権処理について出版社側のフォローは無い。
(3)よって、著作権処理は著者が判断して行うが、相手によっては出版社の公的な対応が求められる。
(4)(1)から(3)での出版社の対応状況や印刷時の対応を見る限り、出版社の著作権への意識は低い。
だから現在、生成AIと著作権の関連や問題点などが様々に指摘されていますが、問題点が指摘されているということは著作権への意識が高いという点で、逆に好ましいと私は思います。出版界のほうが著作権への意識は低いです。
もちろん出版社によって意識の高低は様々だとは思います。でも、もっと法的に高レベルの意識が必要ではないでしょうか。
例えば上の(3)「著作権に詳しくない著者に対し、著作権処理について出版社側のフォローは一切無い」について思うことをひとつ書いてみます。
コラム241号に書いたとおり、原稿の専門的な内容については、データベース検索の専門家のかたなど4名に内容のチェックをお願いしました。そのチェックをお願いしたかたのひとりから、次のような指摘を受けました。p.23 に芥川龍之介の「羅城門」の冒頭を引用したのですが、その引用中に記載される「雨やみ」という表記は間違いだから「雨止み」に直しなさいという指摘でした。
まず芥川龍之介の著作権について書くと、私の原稿執筆時、既に芥川龍之介の著作権は消滅しているので引用は問題無いです。ただし著作者人格権として著作権法第六十条「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」と「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」を考慮すると、芥川龍之介の「羅城門」の引用として記載するなら、著作権における同一性保持はしなければいけない。とすれば芥川が書いた「雨やみ」を「雨止み」に改変しないのが原則です。
表記の間違いの指摘をされたかた(仮にAさんとします)へ、このように著作権に関連した説明をしたのですが、例えばAさんが何かしらの著作をされた場合、著作権が存続している著作物の引用の際に、著作権法に詳しくないAさん独自の判断で「雨やみ」を「雨止み」に改変して記載してしまう可能性は十分にあるわけです。このような無知による違法行為をプロとしてチェックするのは出版社で行うしかないと思うのです。
私自身は著作権に対する自分の知識や勉強や確認で慎重に対応しましたが、所詮素人判断です。出版契約書の条項ひとつで著作権処理を著者に丸投げするのではなく、出版社は著作物を扱うプロとして著作権法への高い意識が欲しいと感じます。たぶん表立って問題が指摘されていないだけで、著作権処理が正しく行われていない著作物は多いのではないかとも思っています。
今回のコラムで紹介した出版契約書には著作物名(書名)と 著作者名(著者)が必ず記載されます。私が最初に受け取った出版契約書では著作者名が私の名前ではありませんでした(!)。たぶん私の前に使った出版契約書を修正して作成したのだと思われますが、この契約書では契約できない旨の文書ともに出版社へ返送しました。2回目に受け取った出版契約書は間違いが無かったのですが、これに限らず、国立国会図書館へ著作物転載の許可願いの書類を送ってくださいとお願いしたのに「国立国語研究所に送ります」とメールが届くし、最初に印刷した1500部は奥付の書名がミスプリントだったとのことで、全部数刷り直しで発行が遅れたし。今回のコラムに書いたように、最初の校正刷りは指示が全く守られていなかったことも含めて、出版社の仕事ぶりの不手際は挙げていくとキリが無いです。
出版社からの執筆依頼メールには情報検索の本として「〇〇先生の本を超えたいと思います」などのカッコ良い言葉が連なっていましたが、出版社の実際の仕事はぶりは大変残念な状態でした。拙著の出版社のひつじ書房さんはビジネス支援図書館推進協議会の理事ですが、ビジネスの基本のひとつは仕事相手と信頼関係を築くことです。信頼関係を築くためには誠実や正直、真面目さなどが必要ですがこれらを実際に行うのはカッコ悪さが伴います。そのカッコ悪いことがちゃんとできるのが大事。本の最後に書いた「カッコ悪いことをちゃんとやれるひとってカッコ良い」は仕事の基本だと思っています。
私の場合、本を書いていて何が一番大変だったかと言えば、出版社にちゃんと仕事してもらうのが一番大変でした。一般的に本の謝辞には編集者への感謝の言葉が書かれることが多いです。私もできれば編集者への感謝の気持ちを書けると良かったのですが、私の場合は謝辞に編集者や出版社のかたを入れる気になれなかったのが自分でも残念です。