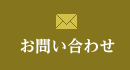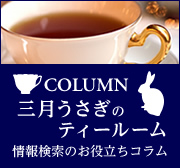情報検索コラム
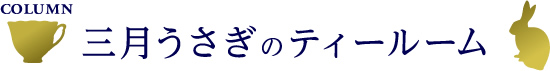
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -理由や根拠を上手に説明する-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回のコラムも書籍執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてみたいと思います。
コラム241号に書きましたが拙著『社会人・学生のための情報検索入門』執筆にあたっては、様々な分野の専門家の皆さんに執筆内容のチェックをしていただきました。検索システムの説明内容や検索例は検索システムの提供元(国立国会図書館、国立情報学研究所など)全4機関に内容の確認をお願いしました。また執筆内容の専門的な記述については、データベース検索の専門家のかた3名(特許検索・技術文献検索専門のかた2名、化学分野・外国文献検索専門のかた1名)、図書館情報学の大学教員のかた1名の全4名のかたに内容のチェックをお願いしました。チェックして頂いた内容をもとに再確認や修正を行いました。
皆さんご多忙な中、遅滞なくチェック結果やコメントをくださいました。大変感謝しています。ただしチェック結果やコメントを頂いた中で、じつは少し困ったこともあったのです。
何が困ったのかというと、私の執筆内容に異を唱えるコメントを頂いたときに、その理由や根拠が示されないものがあったことです。異を唱えるコメントの理由や根拠が示されないから、そのコメントの妥当性が私には判断できない。今回のコラムでは理由や根拠を示せない状況について詳しく見ていくことにより、理由や根拠を上手に説明するためのヒントを書いてみたいと思います。
根拠が示されない例:「国立国会図書館の利用」へのコメント
上に書いたとおり多くのかたからチェックやコメントをいただいたなかで、異を唱えるコメントの理由や根拠が示されないために妥当性の判断ができなくて困ったのは、図書館情報学の大学教員のかたのコメントでした。
コメントには基本的に理由や根拠が示されず、結論だけが赤ペンで記入されていました。だから理由や根拠を推測しながら判断しました。まずひとつめの例です。
●拙著p158「c.最終手段は国立国会図書館」 ( )カッコ内はこのコラムでの付記
当初の記述「国会図書館を(情報入手の)最終手段としたほうが良い理由は、(途中略)国会図書館は「国会図書館」という名前が示すとおり「国会(国会議員)」がそもそものサービスの対象です」に対して赤ペンでのコメントは「違います。国民にもサービスしています」でした。
私が国会図書館を最終手段としたほうが良いと書いた理由は、国会図書館を一般のかたが最終手段でもないのに気軽に利用するといのは、例えるならちょっとした風邪で総合病院へ行くようなものだからです。風邪をひいたくらいなら基本は一般のクリニックなどへ行くわけです。そして風邪ではなく、大きな病気だった場合はクリニックから総合病院へ紹介してくれます。これを図書館利用に置き換えるなら、学生などが一般的に行う調査なら、大学図書館や都道府県立図書館を使うのが基本です。そして大学図書館や都道府県立図書館で調査しきれない専門性が高い内容などの場合は国会図書館の利用を検討することになります。
国会図書館はもちろん18歳以上なら誰でも利用できます。ただし国立国会図書館法では第二条に「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。」と書かれている。この条文を「国民にもサービスしています」と解釈して利用するのか、それとも「日本国民」は、「国会議員」「行政及び司法の各部門」の後に記載されている点に気を付けて利用するのかで変わってくる。
特に同法第二十一条に「国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。」とあります。つまり「日本国民がこれを最大限に享受する」の前提として「両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り」がある。
というわけで赤ペンでのコメント「違います。国民にもサービスしています」の根拠は国立国会図書館法だろうな、と推測しました。ただし私は司書課程で国立国会図書館法を学んだときに、国会議員や行政、司法部門へのサービスは一般国民へのサービスに優先されると学びました。改めて条文を読んでみましたが学んだ内容は間違っていないと思いましたので、最終原稿は「国会図書館は「国民」もサービス対象としていますが、「国会図書館」という名前が示すとおり「国会(国会議員)」がそもそものサービスの対象です」としました。
理由が説明されない例:「査読」へのコメント
ふたつめの例です。
●拙著p183「コラム:学術雑誌の「査読」ってご存じですか」 ( )カッコ内はこのコラムでの付記
このp183のコラムで「学術雑誌の掲載される論文はその雑誌に掲載するかどうかの「査読」が行われます。(途中略)この査読で合格した論文のみが、学術雑誌に掲載されます。(途中略)「情報の信頼性」という観点からは、一般的に査読が行われている雑誌のほうが信頼性が高いとみていいでしょう。」と書きました。
この記述についての赤ペンでのコメントは「そんなことはありません。単に査読が行われたというだけのことだと思います」でした。
赤ペンでのコメント「そんなことはありません」は「査読が行われている雑誌のほうが信頼性が高い」を否定しているのだと思います。この否定の理由が分からなくて困りました。
例えば『学術コミュニケーション入門 : 知っているようで知らない128の疑問』(※参考書籍)のp70に「査読(ピアレビュー)は学術コミュニケーションの世界ではたいへん重要な概念で、一名、もしくは複数名の著者と同じ分野の研究者が依頼を受けて批評や意見を述べるという、出版前に行われる知的品質管理のプロセスです。」と書かれています。この記述に限らず、学術雑誌の査読について事典や辞典、インターネット検索で確認しても、基本的にはほぼ同様の記述をしているものが多い。ChatGPT も「査読は学術研究の品質と信頼性を維持し、学問の発展に貢献する不可欠なプロセスです。」と回答してきました。
査読にももちろん問題点はあり、上述の『学術コミュニケーション入門 : 知っているようで知らない128の疑問』でも様々な問題点が指摘されていますが、査読は「知的品質管理」であり「品質と信頼性を維持」と理解するのが基礎的な理解です。執筆当時も他の情報を様々に確認しましたが、情報検索入門での基本的な説明としては「査読が行われている雑誌のほうが信頼性が高い」という記述で間違っていないと思いましたので、修正無しで最終原稿としました。
なお赤ペンでの否定コメント「そんなことはありません」について私の推測では、先生は日常的に論文に接していらっしゃるので、査読を通った文献に信頼性の低い論文があったとか、査読を行わない雑誌に質の高い論文が掲載されているなどの具体例をご存じなのではないかとも思いました。できれば否定コメントととともに、そのような具体例を理由として示していただけたなら参考になったし、私の勉強にもなったと思います。今、思い返しても根拠や理由を教えて頂けなかったのは残念だったと思います。
根拠や理由を上手に説明するためには、相手の立場に立って情報発信する
ここまでで根拠や理由が説明されなかった例をふたつ紹介しましたが、この他にも先生のコメントは根拠や理由が分からないものが多くて判断に困りました。それらのコメントについてご多忙な先生に根拠や理由を確認するわけにもいかないので、大体こういう理由だろうなと推測しながら判断しました。
情報の信頼性判断のためには根拠や理由が必要です。今までのコラムでは情報の信頼性の確認方法について書いてきました。これを逆から言えば、自分が情報発信する場合は発信した情報の根拠や理由を示す必要があるということです。
上の項で紹介した書籍執筆時のふたつの例に限らず、発信した情報、意見や考察、判断などの根拠や理由が示されないというケースに接することは珍しくありません。
自分の発信した情報などを相手に信頼を持って受け取ってもらうためには根拠や理由を上手に説明する必要があります。この説明を上手に行うためのヒントをいくつか書いてみます。
自分が情報を発信するということは、その情報を受け取る相手がいるということです。だから情報を受け取る相手の立場に立って情報を発信する。これが出発点です。
根拠や理由を上手に説明するヒント1:情報を確認するクセをつける
情報を受け取る相手の立場に立ったときに、根拠や理由を説明する必要があると思うかどうか。また上手に説明できるかどうか。そのためには普段から自分自身が情報入手にあたって根拠や理由を確認するクセをつけているかどうかが最も大事だと思います。
というのも、情報を受け取っても根拠や理由を確認するかたは少ないと感じています。水道の蛇口から水を得れば良くて、その水源は気にしないみたいな印象です。言ってみればそれが普通でしょう。私が特許情報室に勤務していたとき、利用者のかたから例えば「特許の権利期間は何年ですか」と訊かれた場合は、特許法や特許制度の入門書などを案内して「現行法では特許出願の日から20年と書かれています」と回答しました。この回答に対して質問者によっては「こんな簡単な質問はあなたが回答してくれれば良いのに、いちいち本を持ってくる」と、うっとしがられることもありました。図書館や情報室は情報提供が仕事です。問合せへの回答は本や文献、ウェブサイトの記述(情報)を提供します。本の記述を確認することにより情報の信頼度が分かるし、この疑問(特許の権利期間)以外に何か分からないことが出てくれば自分で確認することもできると思うのですが、そうは思わないかたもいるわけです。
とはいうものの疑問への回答だけ得られれば良いというのが一般的な感覚だと思います。今までのコラムでも情報の信頼性の確認方法を様々に書いてきましたが、実際に確認しようとするかたは少ないと思います。でも仕事などで相手に説明したり意見や見解を提示するときは根拠を示すことも必要になります。そのためのトレーニングです。何か気になったことがあったとき、少し立ち止まって根拠や出典を確認してみる。そんな程度で構わないと思います。ニュースを読んでいて分からない用語を調べるとか、地名を地図で確認するとか、そんなちょっとしたクセをつけるところから始めるのが良いと思います。そんなちょっとした確認を続けることにより、いろんな辞典や事典の特徴がわかってくるし、ウェブ検索で確認するときのコツなども身についてくるものです。そして自分の発信した情報の根拠を示すことにも慣れてくる。
コラム250号に書いたような思考停止状態は「回答だけ得られれば良い」で終わってしまう状態ですが、思考停止の思考回路のかたは自分を説明する能力も育ちにくいのかもしれません。例えば上の項で紹介した図書館情報学の先生は「ウィキペディアは信頼性に劣る(コラム242号参照)」という一般的な説を検証せずに信じているかたでした。そして私の原稿に異を唱える先生のコメントは根拠や説明が示されませんでした。先生も仕事で論文を読んだり書いたりするときは引用を確認したり事例を示したりしていらっしゃるのではないかと思います。
実際、サーチャーは普段の仕事で調査依頼者などに技術内容の確認などを行いますが、メールでの回答をいただくとき、その回答の理解の助けや根拠となるURLなどを付記してくださるかたが少なくありません。このような回答をくだだるかたは、自分自身が普段から様々に情報の確認をされているのだろうなと思います。
そして自分の発信しようとする情報の根拠を確認することにより、自分の発信しようとした情報の間違いや不備が分かる場合があります。さらに確認の過程で新たな学びがあることも珍しくありません。普段からいろんな情報発信をされているかたなら、確認過程でこのような経験をされているかたは多いのではないでしょうか。
根拠や理由を上手に説明するヒント2:相手の分からなさが分かるかどうか
そしてもうひとつ。相手の立場に立って説明する意識を鍛えるためにには、説明しなくても通じる相手だけ、例えば社内の人たちだけと情報交換しているような状態だと鍛えられません。言い換えると、分からないひとの分からなさが分からないという状態では、相手に分かる説明はできないということです。
これも普段の仕事で感じることです。調査の依頼を頂くときに自分にだけ分かる内容を送ってこられるかたがときどきいらっしゃる。例えば文章がくどくて分かりにくい。くどくても自分が納得した文章ならOKなわけです。また必要な主語が省略されている。これは主語を省略しても自分には分かっているけれど相手には分からないということが分からないのだと思います。また一般的な用語が社内では広い用途、またはやや違う用途に使われていたりする。これを相手に分からないだろうなと推測できる依頼者のかたの場合は自社のカタログを抜粋して添付して「○○は当社の製品ではこのように使います」などの説明をくださいます。でも相手には分からないということが分からないかたは、そのような説明はしてくれません。で、サーチャー側が一般的な用語解釈で初期調査して、これで良いですかと確認すると「こんな常識も知らないの」と調査の不備を指摘してくる(泣)。その常識はアナタの社内での常識であって、一般的な常識ではないのですが、そのこと自体が分かってもらえない。
こんな例に限らず、例えばいろんな会社が参加する事例発表会などで社内用語が使われていて意味が分からなかったとか、自社で使っている用語が別の意味で使われていたとか、そんな経験はありませんか。自分中心、身内中心で仕事していると他人の分からなさが分からない状態になりやすいと思います。相手の分からなさが分かるようになるためには、身内外のひととの情報交換が必要だと思ます。最初に書いたように私は書籍執筆にあたって様々な分野の専門家の皆さんに執筆内容のチェックをしていただきましたが、そのチェックしてくださったコメントなどから、この説明方法はこのように誤解されることもあるのかとか、この用語はもう少し詳しい説明が必要だな、などと分かることも多かったです。
なお、このようなことを書くと短絡的に「社外の人との交流が大事」と思うかたもいらっしゃると思いますが、それは半分正しくて半分間違って言います。一番大事なことは相手の立場に立って相手の気持ちを推測しようという意識があるかどうかです。そのような意識が無い場合、上で書いたような事例発表会などで他社の社内用語が使われていて意味が分からなかったとか、自社で使っている用語が他社では別の意味で使われていたなどを経験しても自分の学びに結びつきません。普段からより良い仕事をしようという意識で仕事に向き合っていないと学べたはずのことに気付かずに終わってしまう。大事なのは社外の人との交流自体ではなく、仕事に対する自分の意識だと思います。情報室に勤務していた頃、同じセミナーに参加した後輩たちの学びかたを見ていると、意識の有る無しで学んだ内容にかなりの差があると感じました。大事なのはやはり仕事に向き合う意識、そして相手に向き合う意識だと思います。
参考書籍
※参考書籍1
書名:学術コミュニケーション入門 : 知っているようで知らない128の疑問
著者:リック・アンダーソン(宮入暢子 訳)
出版者:アドスリー 丸善出版 (発売)
出版年月:2022年10月
※参考書籍2
書名:データブックオブ・ザ・ワールド : 世界各国要覧と最新統計
巻次:Vol.36(2024)
出版者:二宮書店
出版年月:2024年1月
何か気になったことがあったとき、少し立ち止まって根拠や出典を確認してみる・・・ニュースを読んでいて分からない用語を調べるとか、地名を地図で確認するとか・・・と、今回のコラムで書きました。念のためお伝えしておくと、実際に人前で調べたり確認したりすると、周りのひとに嫌がられることが多いです。その点はご注意ください。
私の場合はサーチャーの職業病(?)みたいなもので、分からないことがあるとその場で確認しないと気が済まない。例えば雑誌を読んでいて知らない英単語があると、仕事机の上の英和辞典をひきに行く。パソコンで動画を見ていて外国の歴史的な説明があったときは、いったん動画を止めて書棚の『データブック・オブ・ザ・ワールド』(※参考書籍2)で、その国の略史を確認する。これを人前でやると大変嫌がられます。そんなこと調べるのって普通なの?と言われる。普通かどうか知らないけど調べないと分からないままじゃん、と思う。今調べなくてもいいのにとも言われる。でも後で調べようと思っても、そのときは調べようと思ったことを忘れてると思うから、そのときに調べないと知らないままになると思う。だから知りたいと思ったときに調べる。でも嫌がられます。
というわけで、なるべくこっそりと自分だけでいろいろ調べるようにしています。ちなみに『データブック・オブ・ザ・ワールド』は毎年新しい版が発行されます。参考書籍2に紹介したものは、このコラム執筆時(2024年5月現在)の最新版で2024年版です。出版社の二宮書店は、地理の教科書が専門の出版社だけあって各国の地勢や気候をはじめ略史や経済、また様々な統計データが分かりやすく整理して記載されています。簡単な確認にはお勧めできると思います。