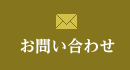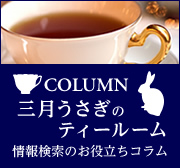情報検索コラム
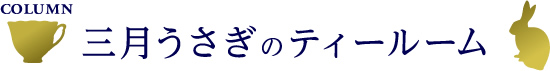
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -知ったかぶりの言葉の信頼性-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回のコラムも書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてみたいと思います。
私は今までに何回かセミナーや講演などで多くのかた、特に知財部門や情報部門のかたから質疑を頂きました。また現在も調査の仕事にあたって、企業の知財部門や調査担当者のかたと様々にコミュニケーションをとっています。そんななかで気になるのは、多くのかたが知ったかぶりで用語を使っていることです。しかも自分が知ったかぶりで使っているという自覚がない。さらに言うと、知ったかぶりの用語であるにもかかわらず格好良いと思う、もしくは便利に使っている。これは(じつは私を含めて)世間によくあるケースなのですが、できれば知財部門や情報部門のかたには、してほしくないなと思います。
世間で使われるカッコよくて便利な用語を安易に使うと自分の信頼度を下げてしまいます。今回のコラムはこの点について書いてみます。
「つなぐ」と「結ぶ」
拙著の1ページ目。最初に書いた「1 はじめに」の「1.1」のタイトルは「レポートの「テーマ」と「検索」をつなぐ技術を身につける」でした。
このタイトルに使った「つなぐ」という言葉ですが、じつは「つなぐ」にしようか「結ぶ」にしようか迷いました。ここで「つなぐ」を使うことにした理由は次の2点です。
・原稿執筆当時(2000年代半ば)は「つなぐ」よりも「結ぶ」が好まれていて、よく使われていた。
・「結ぶ」は結び目ができる印象。「つなぐ」は接続する印象でインターネット環境にも合っている。
今回のコラムに関係するのは最初の理由。「つなぐ」よりも「結ぶ」が好まれていて、よく使われていたので「結ぶ」は使わない、と決めたことです。なぜ使わないのかというと、多くのかたが好んでよく使う用語といいうのは用語の概念が広がりやすいため、受け取る側の理解が曖昧になりがちだからです。参考としてコラム258号で紹介した国立国会図書館の
NDL Ngram Viewer で「つなぐ/結ぶ」を検索すると、「結ぶ」のほうが以前からよく使われていたことが確認できます。
※注意:NDL Ngram Viewer のページ内で説明されているとおり「図書については刊行年代が1960年代まで、雑誌については刊行年代が1990年代までの資料を主に対象」のため2000年以降は検索されるデータがほぼ無く、対比の確認はできません。
というわけで原稿執筆時は流行らない、皆さんが好んで使わない「つなぐ」にしたのですが、書籍発行の2009年の2年後、東日本大震災の後で「つなぐ」が大変よく使われるようになってしまいました。
「つなぐ」や「つなげる」で表現すると好感度が高いとなると、誰もが使いたがる。なんだか私の本も、この流行りに乗ってしまった印象になってしまって不本意でしたが、問題は「つなぐ」という言葉の意味です。
ひとたび「つなぐ」や「つなげる」が流行ると、人と人が会うのも「つなぐ」だし、通信回線の接続も「つなぐ」だし、流通でモノが送られるのも「つなぐ」だし、本来は「つなぐ」以外の用語で説明するべき事柄が「つなぐ」で表現されるようになる。そして用語の概念が広がって、よく分からないときは「つなぐ」を使って、良さげな表現をするひとが増えてしまう。言葉の流行り廃りはあるものなので、これはしかたないことなのですが、情報部門のかたには流行り言葉を安易に使ってほしくないなと思います。
用語の具体的な意味を確認するクセをつける
以前のコラム181号で「遠心力」という用語の意味を確認することについて書きました。
コラム181号では「「遠心力」って学校で習ったし、つい知っているつもりでいるわけですが、ちゃんと説明しなさいと言われたら、説明できますか。このような、知っているつもりでいて実はよく分かっていない用語や事柄に気づく。これも大事なことです」と書きましたが、このような基本的な用語でも、自分がその用語の意味をキチンと説明できないと気付くのは難しいものです。
自分が分かっていないことに気付かないまま調査を進めるのは当然ながら危険です。例えば「遠心力」の意味がよく分からないまま「遠心力」という用語に注目して特許調査を進めた場合、公報の中に次のような文章が出てきたとします。例として洗濯機の脱水の技術です。
「脱水工程の場合、上記クラッチ13が入、ブレーキが解除、排水弁が開の状態が維持され、ブレーキが解けた脱水軸4は駆動軸からクラッチ13を介して回動力が与えられて回転槽3が高速回動し、脱水が行われる。」
(出典:特開平07-323183 / 洗濯機)
これは遠心力により洗濯物の脱水が行われることが書かれていますが、この特開平07-323183には遠心力という用語は使われていません。さらに、コラム181号では先輩が遠心力について「回転するとき外に向かっていく力のことだ」と説明してくれたわけですが、この特開平07-323183では「回転」だけでなく「回動」という用語が使われています。特に遠心力に関連する動きは「高速回動」と記述されています。
このときに「遠心力」や「回転」という用語に頼って調査すると、この公報が遠心力について書かれているということを見落としてしまう可能性がある。さらに検索のときも、用語をキチンと理解しないまま単に「遠心力」という用語を使って検索すると、この公報はヒットしないことにもなります。
「コミュニケーション」って何?
ここで少し説明の仕方を変えてみます。
このコラムの最初に「企業の知財部門や調査担当者のかたと様々にコミュニケーションをとっています」と書きました。意地悪な質問ですが、この文に使われている「コミュニケーション」は具体的にどのようなことなのか説明できますか。実際は、調査の依頼メールが届いて、調査内容のメールが届いて、電話やWEB会議で詳細を確認して、進行スケジュールを打ち合わせて、調査中に依頼者のかたから調査内容に対する追加の情報などがメールや電話で届いて、私から確認事項をメールや電話で問合せて・・・という諸々のやりとりの全てが含まれます。
「企業の知財部門や調査担当者のかたと様々にコミュニケーションをとっています」という一文で、これらのことが具体的に全て正確に伝わるわけではないのに、書いた人は伝えたつもりになるし、読んだ人も疑問なく分かったつもりになる。しかもコミュニケーションと言う用語は「連絡」「意思疎通」「伝達」などの意味を全て曖昧に含んだうえで、格好良く使える。この「格好良く」も「クールに」とか「スマートに」という言葉を使うとクールな言い方になる(笑)。
さらに別な面から「コミュニケーション」という用語を見ると、調査の場合と違って、友人などとの個人的なコミュニケーションの場合は、全然違う事柄になる。相手の気持ちを推し量って言葉をかけるのもコミュニケーションだし、話しを丁寧に聞くのもコミュニケーション。メッセージを送信するのもコミュニケーションだし、旅行のお土産を届けるのもコミュニケーション。「コミュニケーション」は便利に使える言葉の一例です。
「コミュニケーション」という用語に限らず、日常で使う用語はそんなに厳密に意味を定義して使う必要はないと思います。でも、調査の仕事では不可です。用語の意味を確認することが習慣になっている知財部門や情報部門のかたならば、流行り言葉や便利な用語をなるべく安易に使わないかたであってほしいと思います。
さてアナタは「企業の知財部門や調査担当者のかたと様々にコミュニケーションをとっています」という一文が ”この書き方だと何をやってるのか分からない” と頭の中で引っかかったかたでしょうか、それとも疑問なく読んだかたでしょうか。
流行り言葉や便利な言葉を安易に使わないというのは難しいもので、 私も今までのコラムのなかで様々に使ってしまっていると思います。また普段の調査のなかでも分かったつもりで調査を進めていくと、じつは分かっていなかったと気付くことは多いです。流行り言葉や便利な言葉を安易に使ってしまったとか、この用語を自分は分かっていないとか、自分のやっていることに自分で気付けるようでありたいと思っています。
私が調査の仕事を始めた頃は、今回のコラムでも書いたように「遠心力」という用語ひとつでも先輩から「ちゃんと分かってる?説明してみて」と言われると説明できないことばかりでした。そんなわけなので、自分が分かっていないことに気付かないままでいるというのは実際は多いと思っています。最初に書きましたが、分からない言葉を分からないことに気付かないまま使うと自分の信頼度を下げてしまいます。自戒を込めて今回のコラムを書きました。