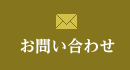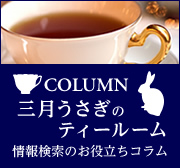情報検索コラム
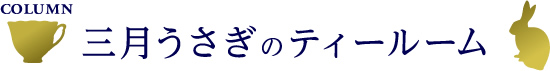
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -バイアスによるミスリード-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回のコラムも書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてみたいと思います。
書籍執筆に限らず講演やセミナー、またこのコラムも含めて様々に情報発信していると、いろんな方から感想や意見、質問などを頂きます。頂いた感想などは私にとって参考になったり勉強になったりするので有難いのですが、中にはやや残念に思うこともあります。何が残念なのかというと「伝えようとした内容が伝えたかったとおりに伝わっていない」という点です。私が伝えたかったとおりに理解していないかたがいるのです。
これは私の文章力や構成力などの不足によるものもあると思うので、何回か見直してミスリードされないように注意します。それでも ”こんなに注意して書いても分からないのか・・・” と落胆することは多いです。ミスリードの原因は読み手側のバイアスです。バイアス(bias)は「先入観」や「偏見」という意味です(参考:『ジーニアス英和辞典 第4版』発行/大修館書店)。何かしらの記事や文章を読むときに自分のバイアスがかかるとミスリードすることがあります。
仕事で何かしら読むときにミスリードは避けたい。特に特許調査のときにバイアスによる特許公報のミスリードが行われた調査報告を作ってしまったなら、相手(お客様)に迷惑をかけるし自分の信用に関わります。
というわけで今回のコラムは情報信頼性判断のヒントのひとつとしてバイアスとミスリードについて書いてみます。
ミスリードの例:図書館による「本は信頼性が高い」の根拠としての引用
大学図書館が学生に向けて図書館利用の利点を説明するときに「本はインターネットよりも情報の信頼性が高い」の根拠として、拙著を引用されたことがありました。拙著を読んでくださったのはありがたいことなのですが説明文は「本や雑誌は、基本的には出版社から出版されています。編集者などのチェックが入ってから出版されています。だから本は数ある情報源に比べて信頼性は高いのです」という趣旨の文で、この箇所の参考文献として拙著が挙げられていました。
これはミスリードによる案内です。何がミスリードかというと「本は信頼性は高い」としか書いていない点です。
拙著p.180「3.10.2 本の信頼性レベルを判断する」に「基本的に、本の信頼性は高いです。本は出版社が発行します。そして出版社には「編集者」がいます。(途中略)本は編集者が選んだ「著者」によって書かれ、編集者が目を通し、著者による適切な書き直しを経た後、「出版社」の責任で発行されます。(途中略)つまり本は、数ある情報源のなかでもかなり信頼性が高い性質を持っているといえます。」と書きました。
図書館のかたが書いた「出版社から出版されています。編集者などのチェックが入ってから」や「数ある情報源に比べて」などの文言は拙著の文を参考にしながら書いていらっしゃるなと思います。でも拙著ではこの後に「しかし、本だからといって100%すべての本が信頼できる内容だとは限りません。」として本の信頼性判断の方法を書きました。つまり本も信頼できない内容のものがあるとか、本の信頼性判断の方法を知っておく必要があるなど書いたのですが、図書館のかたはこの点を学生に案内していませんでした。
このミスリードが発生したバイアスは次の2点です。
(1)学生に図書館の本を利用してもらいたいと思う
(2)著者(味岡)は図書館司書資格があるから図書館に対して肯定的な著者であると思う
まずひとつめのバイアス「(1)学生に図書館の本を利用してもらいたいと思う」です。すでにインターネットから情報入手することに慣れている学生の皆さんに、あえて図書館を使ってもらうためには本の重要性をアピールしたいのが図書館の立場です。図書館の本を利用してもらいという気持ちが強いと、拙著の「基本的に、本の信頼性は高いです」に我が意を得たりと思う。そしてそれを否定する箇所、「本だからといって100%すべての本が信頼できる内容だとは限りません」は目に入らない(目に入れたくない)。そして読み落としによるミスリードが発生します。
そしてふたつめのバイアス「(2)著者(味岡)は図書館司書資格があるから図書館の本に対して肯定的な著者であると思う」。図書館司書資格があるからといって図書館の味方だとは限らないのです。司書資格があって図書館で仕事したことがあるからこそ図書館や本の不利点も分かっているわけです。今までいろんな方向から図書館にか関わってきた経験から、正直なところ私は図書館にあまり良い印象は持っていません。でも司書資格があるなら図書館に肯定的だという思い込み(バイアス)をもって読むので「本だからといって100%すべての本が信頼できる内容だとは限りません」と書いてあるのに読むときに排除してしまう。このようなミスリード、つまりこの著者ならこういう考え方のはずだという思い込みによるミスリードは、普段多くのかたが行っている可能性があると思います。
というわけでバイアスがかかると本来読み取るべきことを読み落としたり、違う解釈のしかたをしてしまったりするのです。
バイアスがあってもミスリードしなければ良い
ならば何か読むときはバイアスがかからないように読むのが良いのかというと、逆にバイアスをかけて読んだほうが良いときもあります。
例えば特許公報を読むとき。特許調査で数百件から数千件の公報を効率良く読むためには、バイアスを書けながら素早く理解する方法があります。例えば機械の制御について調査するとき、出願人名(会社名)を見て機械メーカーならば機械の構造も制御も書いてあるかもしれないけれど、コンピュータ関連の会社ならば制御について書いてある可能性が高い。また特許分類を見ていく方法もあります。「B23Q 工作機械の細部;構成部分」が筆頭分類なら機械の装置の方向からの発明、また「G05B 制御;調整」ならば制御に特徴があるのだろうなどと予想(バイアスをかける)しながら読むと、素早く理解できる面があります。
必ずしも予想が正しいわけではないのですが、予想(バイアス)に対する答え合わせをしながら読んで、合っていればOKで、その判断に従って読む。でも違うならば少し注意して読む、などの読み方をします。特許調査なさっているかたは皆さん自分なりのバイアスのかけ方があると思います。バイアスをかけながら素早く読み取るというのはバイアスの利点のひとつです。また1件の公報を精査するときもバイアスをかけながら読む方法があります。一般的なのは要約を読んで大まかに技術内容を頭にいれてから明細書を読む。また図面にザっと目を通してから明細書を読むという方法をとるときもあります。
だからバイアスそのものが悪いのではなくて、バイアスによるミスリードが問題なのです。
バイアスによるミスリードとしては例えば特許の無効資料調査(特定の特許権を無効にする資料を探す調査)の場合、「特許庁の審査官が調査したんだから探しても無いだろうな」というバイアスをかけて読む。このようなバイアスをかけながら読むと、関連する内容が書かれているにも関わらず見落とすことがあります。また(失礼な書き方で申し訳ないのですが)中国の特許だからレベルの低い内容だろうとバイアスをかけて読んでしまったけど、じつは大事な技術が書かれていたということもあります。
また多数の特許公報をバイアスを書けながら素早く読んでいって「こういうことが書いてある」と判断して拾いだした公報を改めて精査すると、素早く判断したはずの「こういうこと」が理解違いだった・・・ということもあります。特に調査の最初の段階での技術理解のときに思い込み(バイアス)による理解間違いがあった場合は、調査が最初からやり直しになることもあります。
バイアスによるミスリードを防ぐには
バイアスによるミスリードを防ぐ方法は、何を読むかによっていろんな方法があると思います。新聞記事を読むのか、本を読むのか、統計を読むのか、図面を読むのかなどなど、読むものによってかかるバイアスも違うのでミスリードを防ぐ方法も様々だと思います。とはいうものの、一般的な文章理解や特許公報などの文献理解のときにバイアスによるミスリードを防ぐ方法として、次の2点を挙げたいと思います。
ひとつめは「すみずみまでよく読むこと」です。よく読むには時間も使うし頭も使う。簡単に言えばメンドクサイのです。でも例えば最初に書いた「本は信頼性が高い」というミスリードも、拙著を読み進めれば「しかし、本だからといって100%すべての本が信頼できる内容だとは限りません。」と書いてあるのです。また司書資格があるからといって必ずしも図書館の味方とは限らないわけで、例えば拙著のなかではp.141に「有能ではない司書に相談した場合」などで図書館の能力に低さに言及している箇所があります。
いずれにしてもミスリードしている場合は、よく読むと自分のバイアスと嚙み合わない箇所があるはずなのです。特許公報などの技術文献の場合は特にこの「嚙み合わない箇所」に気付くことが大事だと思います。気付いたときは、メンドウでも思い込み(バイアス)を捨てて改めて読み直す。そして理解し直すしかないだろうなと思います。
例えば特定の新聞を読み慣れていると、いつも同じ論調で記事が書かれるのでバイアスをかけて読むクセがついてしまいがちだと思います。できれば自分の思い込みや常識とは違うものを積極的に読むことも大事かもしれません。
そしてふたつめは「自分のバイアスを過信しない」です。例えば特許公報を読むとき、クセになっているバイアスのかけかたがあって、そのバイアスのかけかたでサクサク理解できていても、その方法では間違って理解してしまうこともある。この場合も、やはりどこかに何か「ヘンな箇所」があるはずなので、その箇所に気付くのが大事かなと思います。例えば「こういう内容のはず」と思い込んで目を走らせている中に、その内容ならば出てくるはずのない用語が目に留まる。また例えば「こういう内容」ならば A→B→B’ のはずなのに、よく読むと A→C→B’ になっている。この C って何?と気付くこともある。
これも結局は読んでヘンだなと思えるかどうか。ヘンだと思ったときにイヤでもメンドウでも自分のバイアスを捨てて改めて読み直すしかないと思います。私はいつもそうしています、というかそうするしかないので。
なおついでに書き添えますと、私は世間の常識や規範に沿わない思想の持ち主だったりします。このコラムでも一般的に良いとされていることとは違うことをいっぱい書いています。例えば、善意は否定できないので始末に負えないとか(普通は善意は良いこととされる)、情報検索の練習問題を解いても練習問題を解くのが上手になるだけで検索の実力がつくわけではないとか(普通は練習問題を解くことが奨励される)。これは単にヘソ曲がりで言っているのではなく、実際に自分で経験して考えて、常識や規範が違うと思うから書いているのですが、皆さんからの感想などをいただくと、理解してもらえていないなと感じることも多いです。というわけなので、味岡の書くものはできるだけ常識や規範に沿った読み方をしないで頂けるとミスリードしないのではないかとも思います(笑)。
バイアスとは少し違うのですが、本などを読むときは自分なりの読み方になるのが普通だと思います。例えば『赤毛のアン』を子どものときに読むとアンと同じ気持ちで読むわけです。これを大人になって読み返すと、だんだんマリラの気持ちが分かるようになる。自分が変わると読み方も変わる、というのが本を読み返すときの楽しみでもあります。これは文学作品に限りません。本に書いてあることが昔は理解できなかったけど今読み返すとよく分かるとか、あの本のあそこに書いてあったことはこういう意味だったのかと何年も後で気付くこともがあります。また学生の頃は面白いと思った本だけれど今読むと疑問点があったりします。私が書いたり話したりしたことも、読んだり聞いたりしたときの理解だけでなく、時間が経って皆さんの経験が積まれたときに分かってもらえることもあるかな、と。そんなふうにも思っています。