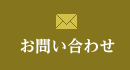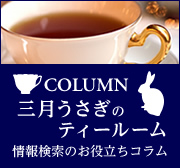情報検索コラム
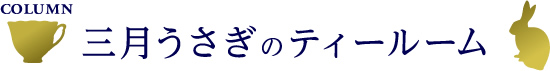
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -質問して情報入手するスキル-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回のコラムも書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてみたいと思います。
拙著『社会人・学生のための情報検索入門』に「3.8 最終手段は人に訊く -ヒアリング-」の項があります。情報検索というと一般的にはキーワードや分類項目などを使ってパソコンで検索するというイメージかと思います。だから情報検索の本にヒアリング方法の説明が書かれているというのは少し違和感があるかもしれません。でも私は情報検索の本を書くならヒアリングについて必ず書こうと思っていました。
執筆当時(2009年)は「訊く」といえば人に訊くことでしたが、現在は ChatGPT などの生成AIに訊く(質問する)ことも日常的になっています。検索もキーワードではなく自然語(自然文)で文章入力する方式の検索システムも一般的になりました。その意味で、執筆当時に比べて現在はヒアリングが検索の一部になっている面が強いと思います。特に生成AIは上手に質問しないと適切な回答が得られないということを実感なさっているかたも多いと思います。
そんな点も含めて今回のコラムでは、質問して信頼性の高い情報を入手するためのスキルについて書きたいと思います。
情報入手のための質問(ヒアリング)のスキルが必要だと思う理由
私は公共の図書館や情報室に勤務していたとき、常日頃から利用者の皆さんから様々に質問されました。その質問のされかたに接していると、質問(ヒアリング)の仕方が上手ではないかたが多いと感じていました。高学歴のかたや大企業に勤務されているかたでも、ヒアリングによる情報入手の基本や訓練などが全くできていないかたがほとんどでした。そのため情報検索の本を書くならヒアリングについて必ず書こうと思いました。
まず率直に言えば、多くのかたは質問のしかたが下手です。下手だと思うポイントは次の2つです。
(1)訊く相手が不適切
(2)訊きかたが不適切
まず(1)の「訊く相手が不適切」ですが、一般的に多くのかたが訊く相手は「身近なひと」です。これについては拙著『社会人・学生のための情報検索入門』のp.167に書いた箇所を抜粋します。
---------------------以下、p.167から抜粋--------------------
情報検索のご相談やご依頼をいただくとき「自分でもヒアリングしてみました」というかたに「どこへヒアリングしたのか」をお伺いすると、たいていは
”ご自分の身近なところ” なんです。”ヒアリング先としてはズレてる” または ”限られた狭い範囲の情報しか持っていない” という相手にヒアリングなさっているかたが大変多いのです。たぶん話を訊きにいくにあたって気軽に訊きにいけたとは思いますが、ヒアリング先としては不適切なヒアリング先を選んでいます。
-----------------------------以上、抜粋----------------------------
拙著ではこの後に続けて、適切なヒアリング先を選定することがヒアリングの第一歩であることを説明しています。適切なヒアリング先というのは、その専門分野の専門機関や専門家のことですが、とにかく訊く相手が不適切ならば、適切な情報は入手できない。この点を理解しておいてほしいと思います。
そして(2)の「訊きかたが不適切」。この不適切さの特徴は「自分の頭に浮かんだ質問をそのまま訊く」ことです。もっとも多いのは、自分の知りたいことだけをピンポイントで質問してくるケースです。これがなぜ不適切かというと、理由は大きく次の2つです。
・なぜ知りたいか、すでに知っていることは何かなど、質問の背景を説明しない。
・自分が何を知るべきなのかが自分でわかっていない。
質問の背景として知りたい理由、また既に入手済みの情報などを説明しなければ相手からの信頼は得られないし、適切な情報入手はできません。この点については特に近年、生成AIへ質問するときに質問の背景を説明することが大事であること実感なさっているかたは多いのではないでしょうか。また質問内容が整理できていないかたも多かったです。上手に質問してくるかたのほうが圧倒的に少なかった。そんなかたの質問内容を整理しながら職員(私)がインタビューする日々だったので、できるだけ学生の時点でヒアリングの基本を学んでトレーニングしてほしいと常々思っていました。学生ならば多少は拙いヒアリング方法でも、教育の一環として接してくれる場合も多いと思うからです。だから学生向けに情報検索の本を書くならばヒアリング方法の説明を必ず入れようと思っていました。
ヒアリングによる情報入手は社会の迷惑なのか
最初に原稿を書き上げた後、執筆内容の専門的な記述について、データベース検索の専門家のかた3名(特許検索・技術文献検索専門のかた2名、化学分野・外国文献検索専門のかた1名)、図書館情報学の大学教員のかた1名の全4名のかたに内容のチェックをお願いしました。このチェックのお願いにあたって「3.8 最終手段は人に訊く -ヒアリング-」の項は、図書館情報学の大学教員のかたにお願いしました。理由は、図書館業務ではヒアリング能力は必須だからです。図書館では利用者からのレファレンス(参考調査)の際、利用者のかたが知りたい情報は何かを聞き出す(ヒアリング)ことを行います。また図書館内の資料、また他館の資料などで回答できなかった場合に、専門機関や専門家のかたへのヒアリングによって情報入手することもあります。だから特にヒアリングによる情報入手に詳しいと思われる図書館情報学の大学教員のかたに、ヒアリングの項の内容チェックをお願いしました。
お願いして返ってきた原稿には赤ペンで「専門家へのヒアリングを大学生に勧めるのは全く適当ではない」と書かれていました。私はヒアリングの基本を学ぶことは必要だと思うし、先生は図書館情報学の教員なのだから、そもそもヒアリング方法を学生に教える立場なのではないかという疑問もあったので「ヒアリングが必要な場合は実際にあります。学生に勧めない理由を知りたいです」という趣旨のメールをお送りしました。
ご回答の趣旨は、学生が文献などから入手できない情報を質問する相手は教員がいるのに教員を飛ばして外部の専門家に質問するのか、とのことでした。そして、きちんと文献検索もしない学生が気軽に分からないことを聞いてくるのは、質問を受ける側からすれば迷惑だとのことでした。
先生の立場から言えば最もだろうなと思います。でもね、社会の立場から言うとヒアリングのトレーニングが無いまま社会に出てくることのほうが迷惑だし、本人にとっても不幸だと思うのです。例えて言えば子どものお使いは社会の迷惑なのか、それとも買い物のしかたを教えるのが大人の責任なのか。ヒアリングや質問の仕方は買い物の仕方ほどには社会的能力として求められないとは思いますが、上の項に書いたように高学歴のかたや大企業に勤務されているかたでも、ヒアリングによる情報入手の基本や訓練などが全くできていないかたがほとんどです。だから迷惑だといってやらせないのではなく、ヒアリング方法をきちんと指導して、それでも失敗して、他の大人に叱られながら学ぶのが大事なのではないかと思うのです。できれば学生のうちに学んでほしい。このようなことは、そもそも迷惑をかけながら学ぶものだと思うので。
ただし全くヒアリングを行わせないわけではなくて、卒論の指導などで先生の知らないことについて図書館の現場の人に相談して、どなたかの話しを聞きにいかせたことはあったとのことです。その場合でも教員がちゃんと仲介をして行かせたとのことだったので、このときに仲介だけでなく訊き方の指導もしていただければとも思いました。一般的には仲介はしても訊き方の指導はしていない。だって訊き方の指導をしているなら、どうして高学歴のかたや大企業に勤務されているかたでも、ヒアリングによる情報入手の基本や訓練などが全くできていないかたがほとんどなのか。
結局私の結論は既に書いたとおり、学生のヒアリングは社会の迷惑だけど、ヒアリング方法を学ばないまま社会に出てくることのほうがさらに迷惑だし本人も不幸。学生時代は数年で終わるけど、その後に数十年の社会人人生が続く。そのことも考えてほしい、です。そして、そもそもヒアリング方法の指導ができる先生は少ないのだろうな、とも思ました。だから余計にヒアリングについて書かないといけないと思いました。
とはいうものの先生の立場も尊重しながら「3.8 最終手段は人に訊く -ヒアリング-」の項のタイトルに「(基本的にはお勧めしません)」と付記しました。そして「3.8.1 ヒアリングをお勧めしない理由」として「(1)特定の個人の時間を奪うことになる」、「(2)ヒアリングから得る情報は「不正確な情報」である場合が多い」などの理由を慎重に書いたうえで、適切なヒアリング方法を案内しました。
書いてあることと書いてないことの関係
調査におけるヒアリングについては以前のコラムで詳しく書いたので、興味のあるかたは次の2つのコラムをお読み頂ければと思います。
コラム第194号 ヒアリング、インタビュー -調査における「訊く力」(1)-
コラム第195号 ヒアリング、インタビュー -調査における「訊く力」(2)-
情報の信頼性という意味でヒアリングについて大きく言ってしまえば、世の中で書いてあることが全て正しいわけではないし、誰かが言っていることも全て正しいわけではない、ということです。なんだ当たり前じゃん、と思いますか。フェイクニュースや生成AIが問題視される前提は、正当に報道されるニュースや写真などが正しいものとされているからです。このコラムでも何回か書いていますが、報道されていることと実際に起こっていることは違う。もちろん報道する側は正しく報道しようとしている面はあると思います。でもどんなに誠実に報道したとしても、情報の取捨選択はあるし、記者の理解間違いも発生する。さらに読んでもらいたいという気持ちから、書くときの言葉も選ばれる。例えば、いつも報道する側のかたが何らかの理由で報道される側の立場に立ったなら、「この報道は違う」と思うはずです。拙著を書くときに参考にした書籍『自分で調べる技術』では次のとおり書かれています。
---------------------以下、※参考文献 p.94-95から抜粋--------------------
思い切って言ってしまえば,資料や文献に載っていることは,この世の現実のごく一部に過ぎません.もちろん,それは取捨選択され整理された「一部」ですから,非常に有益な「一部」であることは間違いありません.しかし,その取捨選択や整理は当然何らかの偏りがかかっているし,限定されています.私たちが今必要としている情報ズバリであればそれでいいのですが,往々にして,文献や資料を調べると,「参考にはなるが,そのものズバリではないなあ」ということが多いものです.今私たちが必要としていることが資料にも文献にもない場合はどうするか.自分の足で調べるしかありません.それがフィールドワークです.
(途中省略)
私たちは何かを調べようというとき,必ず「先入観」を持っています.こういう問題があるはずだ,とか,こういうふうになっているはずだ,といった「先入観」です。「〇〇問題について調べてみたい」という人もいるでしょう.しかし,ここで立ち止まって考えていただきたいのは,「〇〇問題は本当に存在するのか」ということです.
(途中省略)
マスコミが提示する構図や自分の思い込みからなんとなく想定していた「〇〇問題」は,調査するとすぐに崩れることが多いのです。
------------------------------------以上、抜粋-----------------------------------
長くなるので引用はこれくらいにしておきますが、実際にフィールドワーク(聞き取り調査、ヒアリング)をしているかたの書くことは納得できることが多いです。図書館で参考調査すると、本に書かれていることは本当にわずかだと実感します。以前あるかたが「図書館ってこんなに本があるのに、イザ調べると何にも無いね」と言っていましたが、実際そのとおりだと思います。この本では、この後に「誰に聞くのか?」や「メモ術」「聞いた話は正しいか?」などが具体的に書かれてます。私がサーチャーの立場で書いたものとは違う観点から詳しく書かれています。発行は2004年で古いですが、調査の基本的な思想は古くならないので、興味のあるかたはお読みいただければと思います。
いずれにしても私が今までに調査した経験から言えば、本や文献、新聞などに書いてあることが全て正しいわけではないし、誰かが言っていることも全て正しいわけではない。書いてない情報を入手するためにはヒアリングも必要です。そして適切に情報入手するためにはヒアリングのスキルが必要です。さらに入手した情報(言っていたこと)の検証も必要。このスキルや技術が身についているなら、フェイクニュースにも落ち着いて対応できそうかな、と思います。いかがでしょうか。
※参考文献
書名:自分で調べる技術 : 市民のための調査入門(岩波アクティブ新書, 117)
著者:宮内泰介
出版者:岩波書店
出版年月:2004年7月
書籍執筆では検索システムの提供元の方も含めて多くのかたにチェックや確認をお願いして、様々に修正を入れながら書き直しをしましたが、このヒアリングの箇所は真向から「全く間違っている」と書かれてしまって、私にとっては最も衝撃的な指摘でした。なにしろヒアリングのスキルは必ず必要だと信じていたので。とはいうものの改めて振り返ってみると、先生の立場が分かってなかった面もあるし、自分の価値観が必ずしも受け入れられるわけではないということを自覚できたし、自分の勉強になったということで良かったかもしれないと思います。人(またはAI)に質問して情報を入手するということは皆さんも普段から気軽にしていることかと思います。今回のコラムを読んでどう思われたでしょうか。やっぱり先生のおっしゃることのほうが納得できる、というかたも多いのかなとも思います(なぜか弱気・・・)。
ちなみに私自身は学生の頃にヒアリング方法を、どのように学んだのか。コラム本文でも少し触れましたが図書館業務ではヒアリング能力は必須なので、レファレンス(参考調査)の際、利用者のかたが知りたい情報は何かを聞き出すためのやり方や、専門機関や専門家のかたへのヒアリング方法の指導を受けました。特に私の学んだ司書課程では課題として「高校の学校図書館の利用案内を作る」というのがありました。実際の高校の図書館にお願いして、その高校の図書館を見せてもらい、実際に使える利用案内を作るという課題でした。そのときに、外部(高校の図書館)へのインタビューのしかたについて注意や指導がありました。これだけでなく公共図書館行って職員に話を聞く課題などもあり、その都度指導がありました。それでも学生だから相手に失礼なことを言ったりして、今思うと本当に迷惑をかけたと申し訳なく思います。特に私自身は先生に相談もせず勝手に(!)自分の判断で、地元の市立図書館に「実習させてくだださい」とお願いに行ったりする非常識な学生でした。受け入れてくれた図書館のかたには感謝するしかないです。そして実習で学んだことをレポートにして提出したら、先生も怒るどころか褒めてくれました。迷惑かけたことは申し訳ないとは思いますが、良い大人たちに恵まれた学生時代だったなと思います。なお地元の図書館での実習のことは「コラム番外編 夏休みの思い出 -知識と経験と機会と自分-」で詳しく書きました。よろしかったらお読みください。