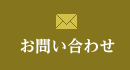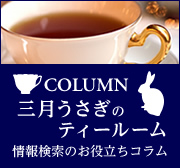情報検索コラム
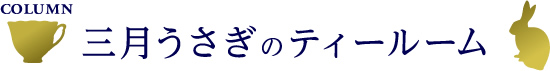
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
情報の信頼性判断のヒント -情報の鮮度を判断するスキル-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回のコラムも書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに、情報の信頼性判断のヒントを書いてみたいと思います。
私の書いた本は情報の検索に関する内容です。情報には必ず「鮮度」があります。本や雑誌、インターネットなどから発信される情報は生中継などでない限り、必ず情報発生時から情報発信時までの時間差、つまりタイムラグがあります。このタイムラグを考えながら情報の信頼性を判断する必要があります。さらに、既に得た情報が時間を経てどのくらい劣化し、信頼性が低下しているか。その点も判断する必要があります。
本を書くときは情報の鮮度を考えながら書きました。今回のコラムでは情報の鮮度を判断するためのヒントを書いてみます。
時間を経て劣化し、信頼性が低下する情報
書籍執筆にあたって編集者から「情報検索の練習問題を入れてほしい」という要求がありましたが、私は断りました。なぜなら情報検索の分野では、書籍執筆時に作った練習問題は時間を経て劣化していきます。本を読む時点には既に使えない練習問題になっている可能性が高いからです。
練習問題が使えなくなる主な理由は次のとおりです。
(1)検索システムがアップグレードされる
検索システムがアップグレードされると検索画面の設計自体が変わることが多いので、本に書いてあるとおりに入力できない場合があります。また検索システムの変更により新しい機能が加わったり、今まで可能だったことができなくなったりします。そして本に書いてあるとおり検索しようとしてもできない、ということが時間を経るごとに増えていきます。さらに最終的には全く役に立たない練習問題になってしまいます。
(2)収録データは常に更新される
検索システムが使えたとしても収録データは常に更新されるので、検索してヒットする情報はどんどん変化していきいます。実際、情報検索セミナーなどで新聞記事検索の練習問題を作ると「ヒット件数がセミナーのテキストに書いてある件数と違う」と言われたことがあります。新聞記事は毎日更新されて新しいデータが収録されていくので、検索期間を指定しない限り、ヒット件数はセミナーのテキストに書いてある件数と違うのが普通なのです。
このほかにも検索システム提供元が変わったり、検索システム自体がサービス終了したり、逆に新しいサービスが開始された、データの収録基準が変わったり、情報検索の分野は特に変化が大きい。そんな中で練習問題を作っても使えるものにならないと判断しました。
時間を経ても劣化しない情報
検索の練習問題は作りませんでしたが、検索例は載せました。検索例は検索のしくみを説明するために載せました。例えば図書館の検索システムで携帯電話について書いてある本を検索したくて、単に「携帯電話」で検索するとタイトルに「携帯電話」が入っている小説もヒットしてしまう。これを避けるために件名検索を使うと携帯電話について書いてある本だけがヒットする。しかも「ケータイ」や「ワンセグ」など携帯電話に関連するけれど、携帯電話という言葉を使っていない本もヒットする、という検索のしくみを説明するための検索例です。
この検索例も検索画面やデータ、また検索に使った用語などもどんどん古くなります。ただし大事なのは、この例で言えば「携帯電話」で検索すること自体ではなく、図書館の本を「件名」で検索するしくみを知ることです。このしくみが理解できたなら、検索例に使った国立国会図書館の検索システムだけでなく、他の図書館の検索システムでも件名で検索できるスキルが身に付くし、国立国会図書館の検索システムが新しくなっても(実際に現時点では全く違う検索画面になっています)件名で検索することにより、ノイズを除いてモレなく検索することができます。
知識や技術は古くなるけれど、意識や思想は古くならない
私は編集者から「情報検索の練習問題を入れてほしい」という要求があったときに「練習問題なんてどんどん古くなるから作っても意味が無い」と断りましたが、そのときに同時に編集者に伝えたのは「スグに古くなるテクニックや知識ではなく、調査や検索を支える思想や意識を書きたい」ということでした。このことは知識重視の編集者のかたには理解してもらえなくて、検索方法を書いてもらえないと困るという趣旨のメールを頂きました。
少し別の話しをします。私が公共の情報室に勤務していたとき、私も後輩たちも様々なデータベース検索のセミナーに参加していました。で、例えば後輩たちが2名、同じセミナーを受講してきたにも関わらず、セミナー受講後にサーチャーレベルの検索ができるようになる後輩と、いつまでたっても受講者レベルの検索しかできない後輩がいるのです。
ここに書いた「受講者レベルの検索」というのは、習ったことだけできる検索です。それに対して「サーチャーレベルの検索」というのは、自分で考えて発展させてより良い検索ができることです。サーチャーレベルの検索ができる子は傍で見ていて、この子は伸びてるなと感じます。
このサーチャーレベルの検索ができる後輩と接していると、セミナーで知識や技術以外のことを学んできていると感じました。例えば特許検索のセミナーでは検索式を考えるときに、公報の発行日を漏れなく指定するために、このコードも指定しないといけないとか、調査漏れを防ぐためには特許分類を使った検索だけでなくキーワードだけの検索で補完すると良い、などの知識を学ぶのですが、その知識と同時にセミナー講師の「検索漏れさせない」というプロ意識を学び取ってきているのです。学び取るというよりは感じ取るという感覚かもしれません。
セミナーで知識だけでなく「検索漏れさせない」という意識や思想を学べた場合、自分で検索するときに漏れの無い検索をしようという意識が働きます。だからセミナーで学んだ検索方法だけでなく、例えば出願人を指定した検索のときにも、漏れの無い検索をするにはどうしたら良いか考えるようになる。こういう子は伸びる。そして伸びる子というのは、どうしたら良いか考えるから、知識を更新していける。鮮度の良い知識を適切に入手しいていけるのです。
適切な鮮度の情報を入手するために
情報検索の分野にに限らず、知識やテクニックは時間とともに古くなっていきます。だから今、仕事する時点で自分が適切な鮮度の知識やテクニックなどの情報を持っているかどうかをセルフチェックできることが大事です。このセルフチェックのためには仕事上の意識や思想が必要なのだと思います。意識や思想を持って、目の前の現実(例えば調査テーマ)に向き合えば、自分の知識が古いなと感じて、新しいやり方を学んでいけるし、単に新しい知識を追いかけて疲弊することもないと思います。
特許や検索の分野で自分の持っている知識が更新されていない、いわゆる古臭い人(!)に接すると、自分が学んだ知識にしがみついているという感じが強いです。しがみついているものを離さないと新しい適切な知識は得られないわけで、そのためには目の前の「今」の現実に向き合うしかないのですが、意識や思想を持っていないと「今」の現実に向き合うことができない。今の現実に向き合うというのは、過去の自分の知識を否定することになるわけで、否定したときに自信をもって知識を更新するためには意識や思想が必要です。具体的に言うなら、漏れの無い検索をしようとか、新しい技術を適切に調査しようとか、依頼者に提供すべき情報は何なのかとか、テクニックや知識以前の思考です。このような思考ができると、この思考をもとに適切な知識に更新していける。
そして、このような思考ができないと単に古臭い人になってしまうか、逆に新しい知識に振り回されるかのどちらかだと思います。
このように思っていたので、私の書いた本では「情報検索の「軸」を決める」とか「正確な主題知識を十分に得る」とか意識や思考について書いたことが多いです。上に書いたように図書の件名検索も、単に検索画面の説明ではなくて、件名を使って検索するということは、その件名が示す概念の分野の本を検索することだという思想を学んでもらえるように書きました。他にも例えば適合率・再現率の説明では、単に適合率・再現率の説明だけでなく、良い検索のためには適合率・再現率をどのように考えるのかを書きました。
というわけで古臭い人にもならず、新しい知識にも振り回されず、適切な鮮度の知識や情報を入手する人になるために意識や思想、思考を持ってほしいと思いながら本を書きました。このことは編集者には分かってもらえなかったけど、読んだかたに伝わったなら幸いです。
今回のコラムのテーマは「情報の鮮度を判断するスキル」ですが、やはり今大事なのは、自分のもっている知識(情報)の鮮度を判断するスキルかなと思います。 近年、リスキリングやリカレント教育などの言葉を目にすることが多くなり、また高齢でも現役で仕事なさっているかたに接する機会も増えてきました。そんななかで良い仕事を行うためには、自分のもっている情報の鮮度を判断するスキルが大事ではないかと感じることも多いです。今回のコラムも、ずいぶんエラソーなことを書きましたが、特許や検索の分野の知識は次々に更新されていくので遅れずについていき、しかも振り回されないようにしないといけない。そんななかで、やはり意識って大事だなと自分自身が思っています。