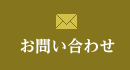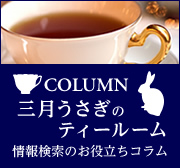情報検索コラム
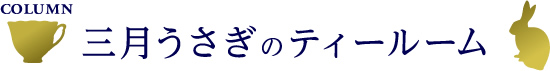
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
ビジネス支援を受ける -知るべきことを知るための dialog-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
この情報検索コラムはサーチャーの仕事についても様々に書いているため、サーチャーを目指すかたも読んでくださっているようです。なかにはサーチャーとして独立して仕事をしたい、つまり開業(フリーランス)したいと思っているかたもいらっしゃるようです。またセミナーや講演などの質疑でも、独立開業を考えていると思われるかたから質疑を頂くこともあります。そのような経緯から今回のコラムもご自分で開業を考えているかたへ、ビジネス支援を受けるときの注意点を書きます。ビジネス支援を受けるための参考にして頂ければ幸いです。
今回のコラムは前半で自分が知りたいことを知るためのヒント、後半で知るべきことを知るためのヒントを書きました。今回のコラムで書きたかったことは後半の「知るべきことを知る」です。前半は以前書いたことを別の事例で検証し直していますので、そのつもりでお読みいただければと思います。
開業は自分が責任と主体性を持つ
前回のコラム264号の最後に「ビジネス支援を受けるヒント」として「ビジネス支援を受けるということであれば、大事なことのひとつは自分の必要な支援は何なのかを明確にすることだと思います」と書きました。「要は受け身で相談に行かないこと、自分の側に主体性を持つこと」とも書きました。
ここで「自分の側に主体性を持つ」と書いたのは、以前に経営コンサルタントのかたとお話しさせて頂いたとき、こんなことをおっしゃったかたがいたのです。「起業したいと言って相談にくるかたがいるんだけど、とにかく何かしたいんだけど何をすれば良いのか分からないと言って相談に来るんですよ」。さすがにサーチャーである私のところにはここまで漠然とした相談は無いので、コンサルのかたは大変だなと思いました。でも起業が「良い」、そして「カッコイイ」とされる風潮が強まると、これも現実だろうなと頷いてしまいました。
このような漠然と人任せに「どうしたら良い?」と受け身で相談に行くのは無責任です。事業を起こす、また開業するというのは簡単ではないので、このような無責任な状態から良い事業が生まれるはずもなく、まずは自分で責任と主体性を持つ覚悟を決めるところから始めることだと思います。サーチャーが情報入手や調査を依頼される立場から言っても、責任感のあるかたからの調査依頼は対応しやすい。特に依頼内容に具体性があることと、調査中の確認事項などへの対応も迅速かつ誠実に対応してくださることが特長として挙げられます。
自分に必要なことを知る、伝えるテクニック
自分に必要なことは何かを具体的にしないといけないのですが、これは調査や検索におけるインタビューやヒアリングのテクニックが使えます。インタビューやヒアリングのテクニックは今までにコラムや書籍に何回も書いてきたので、今回はポイントだけを簡単に書きます。
●参考:インタビューやヒアリングのテクニックについて書いたコラム
コラム第194号 ヒアリング、インタビュー -調査における「訊く力」(1)-
コラム第195号 ヒアリング、インタビュー -調査における「訊く力」(2)-
コラム第254号 情報の信頼性判断のヒント -質問して情報入手するスキル-
ポイントは3点です。情報入手の目的を明確にすること。既に入手済みの情報を明らかにしておくこと。情報入手先や相談先を適切に選ぶことです。「起業したいけど何をすれば良いのか分からない」という相談をこの3点に照らし合わせて見てみましょうか。
まず「目的」。起業の目的が収入を得ることなのか、それとも社会貢献したいのか、単に充実感を得たいのか、何かしら自分の目的があるはずです。調査や検索でも目的がハッキリしなければ検索のしようが無い。目的が明確ではない相談はプロとしては対応できにくい。この点を知っておいてほしいと思います。
そして「入手済みの情報」。これが伝えらえれないかたは多いです。この相談者も伝えていません。起業したいけど何をすれば良いのか分からないという状態であっても、何かしら情報を得ているはずです。相談するときに入手済みの情報を明らかにして、整理して相手に示せる状態にしておくことです。既に入手済みの情報を説明しなければ相手からの信頼は得られないし、適切な情報入手はできません。入手済みの情報を相手に示すというスキルは意識して訓練しないと身にとかない面があります。入手済みの情報が伝えらえれないかたが多いのは、知識重視の学校教育段階ではなかなかこのようなスキルを身につける機会が無いからではないかと思われます。
さらに「相談先を適切に選ぶこと」。この相談者は経営コンサルタントに相談しに行っています。起業という点では適切といえそうですが、経営コンサルタントに相談するのであれば、ある程度は具体的なアイディアが必要です。「起業したいけど何をすれば良いのか分からない」は人生相談(?!)の段階なので、プロに相談する内容ではありません。
なおインタビューやヒアリングが上手にできるかどうかについて、コミュニケーション能力の問題だと思っているかたもいるようですが違います。例えば営業職でコミュニケーション能力が高い方からの情報入手相談。
このようなかたはコミュニケーション能力が高くて話しかたも上手です。自分の欲しい情報を明確に伝えてくるのですが情報入手目的は言ってくれない。だからこちらから訊ねることになります。また最もできないのは入手済みの情報を示すことです。これも調査前にお聞きするのですが、明確に答えてもらえない。入手済みの情報がご自分で整理できていないのです。そして調査報告をお渡しした段階で「これボクも見た」と言う。これが現実です。また「起業したいけど何をすれば良いのか分からない」と言って経営コンサルタントのかたに相談に行ったかたも一般的に言えば専門家に相談するというコミュニケーションがとれています。でもインタビューやヒアリングのテクニックは身についていない。
インタビューやヒアリングを上手に行うためにはテクニックや技術、方法を具体的に身につけることが大事であって、能力という概念とは次元が異なります。コミュニケーション能力はあっても構いませんが必須ではありません。インタビューやヒアリングはコミュニケーション能力の問題だと言うといかにも最もらしく聞こえます。でも現状の事実を見ると違う。物事は知識と概念で語らないことです。知識や概念で語られる最もらしいことを現実や実例に照らすと、じつは違うと分かることは多い。何か語るときは知識や概念から始めるのではなく、事実や実例、実際の現象を確認するべきだと思います。
知るべきこと:相手との dialog で「知る」が深まる
コレが知りたい、情報が欲しい、と思って検索や調査を行うわけですが、実際に調査していくと自分の知るべきことはコレではないということが分かることも珍しくありません。例えば特許調査で技術情報収集する場合も、依頼者のかたから特定のテーマで調査を開始したところ、そのテーマに関連しているけれど依頼者のかたが想定していなかった技術が発見されることがよくあります。特許調査の場合は依頼者のかたも技術の専門家なので、調査報告を行うと依頼者のかたも想定していなかった技術が発見されていることに気付いてくれます。そして、この技術を重要だと判断なさった場合は追加で調査依頼をいただくこともあります。
サーチャーとしては、このようなことは嬉しいです。自分の調査が依頼者のかたの研究開発を広げたり深めたりするきっかけになることもある。ということはアナタがビジネス相談した場合、相談した相手がアナタの知りたいことだけでなく、知るべきことを知るヒントをくれることも十分にあり得ます。というのも、特許情報もビジネス情報も、どんな情報であっても自分の頭のなかで考えているコト以外の情報は当然ながら存在します。良い相談相手(ビジネス支援者)に相談できたなら、その相談相手とのやり取りや対話(dialog)で自分の知りたいことだけでなく、自分の知るべきことが見えてくることもああります。自分の頭のなかで考えている段階が monologue だとすると、その後で行う相手とのやり取りや対話が dialog の段階です。
例えばコラム263号「ビジネス支援を受ける -溺れないためには藁をつかまない-」で良いビジネス支援者の例としてK氏のことを書きました。特定の問題を解決するというアイディアでの新規事業についてK氏に相談に行ったところ、この新規事業で融資を受けるにあたって、特定の問題の発生状況が分かるデータが必要になったという例を書きました。このとき相談に行ったかたは、最初は特定の問題の発生状況が分かるデータが必要だとは思わなかったはずです。必要なのは融資を含めた事業開始の相談だったはずです。ところが相談したところデータが必要だと分かった。このデータが相談者のかたが自分で想定していなかった「知るべきこと」です。良い相談相手に相談できた場合は、このように知りたいことだけでなく、知るべきことも見えてきます。そして念のため言っておきますが、自分のアイディアがダメであることが見えてくることもあります、残念ながら。特許の出願前調査でも自分のアイディアの先行例が発見されることがあるのと同じで、起業のアイディアも調査していくうちに、これじゃダメだなと分かる場合も多いのです。
ただし自分の発明の先行例が発見されたなら、それをもとにさらに良い発明を行うこともできるのと同じで、自分のアイディアがそのままではダメだと分かったなら、そこからさらに良いアイディアを練っていくことも可能です。ダメということを知るのも大事なのです。
私も事務所を開業したばかりの頃は、自分に必要なのは取引先だと思っていました。でも開業後の約3年間、先輩の特許調査を手伝いながら知った自分に必要な「知るべきこと」は、調査における考え方を身につけることでした。特許調査を行うには検索や特許の知識があって、取引先が確保できただけでは良い調査事業は行えない。
例えば無効資料調査のとき、調査した自分としては自分の発見した文献を、つい過大評価してしまいたくなる。コレを見つけた(!)と関連度「高」で報告したくなるけれど、厳しく見れば調査観点と相違する点があるから実際は関連度は「中」。私が関連度「高」と記入すると、先輩は「この構成要件はどこに書いてある?書いてないなら高じゃなくて中だよね。依頼者にヘンに期待させないほうが良い」と手直しされました。私はこのとき、文献の記載内容を厳しく読み取ることや依頼者の立場に立って報告することなどを学びました。このようなことは先輩との対話の中で学ぶ「知るべきこと」です。
もうひとつ例を挙げると「調査は実際に公報を読んだひとだからこそ分かることがあるから、そういう細かい具体的なことをキチンと私に伝えてください」と指導してもらったことです。実際に公報を読んだひとだからこそ分かることというのは例えばコラム221号「特許サーチャーの視点で見るノーベル賞 -青色発光ダイオード-」に書いたような発光ダイオードの調査を行って、新しい公報から遡及して調査していくと1997年頃までは、いろんな会社(出願人)が出てくるけれど1996年から先は日亜化学工業と豊田合成ばかりになる。そして1992年から先は日亜化学工業も出てこなくなって、豊田合成ばかりになる。豊田合成は日亜化学工業よりも先に発明および出願されていたことが実感できる。これはパテントマップを使えばグラフ化できますが、実際に読んで実感するとさらに細かい傾向も分かるものなのです。
これは一例ですが、実際に公報を読むと調査中に想定外のことが分かるという例は多い。さらに調査観点に対してズレた情報をどのように判断したかなども調査中にメモします。また調査にあたって確認した技術内容の知識などもあります。そして「キチンと私に伝えてください」と言われたからといっても、それら全てを先輩に伝えると怒られる(!)のです。調査中に分かった「細かい具体的なこと」のうち、伝えるべきことは何なのかを判断する必要がある。例えば調査にあたって確認した技術内容の知識は自分では大事だと思っても相手にとっては不要な情報だったりするわけで、そのような不要な情報を説明しようとすると「そんな説明を聞く必要は無い」と叱られる。つまり不要な説明で相手(先輩)の時間を無駄に使うなと怒られる。また伝え方も大事です。簡潔な結論を先に書いてから説明を書く。説明も具体例を挙げながら説明する。例えば調査観点に対して想定外の技術だけれど関連性が高いと思われる技術が多数発見されることがあります。それらを参考として調査報告に含める場合は、その技術内容のポイントを説明したうえで、その技術が記載されている代表的な公報番号を例示してから詳細な調査リストを報告します。これも最初は報告しながら言葉で「こういうのがあった」と説明していたのですが、先輩から「どの公報のどこに書いてある?」と確認されるので、報告書に具体的に書くようになりました。
そんなやり取り(対話、dialog)の中で自分の「知るべきこと」、つまり調査のスキルや考え方を身につけていけたと思います。このとき身につけたスキルや考え方は今でも毎日使っています。そして有難いことに依頼者のかたから私の調査は、調査結果の検討内容の共有ができるということで良い評価をいただけたりします。
これを逆から言うと、コラム263号に書いたような残念なビジネス支援者とのやり取りや対話では、自分の知るべきことが見えてこない。しかも残念なビジネス支援者は知識や概念で最もらしいことを言うかたが多いです。上の項では「インタビューやヒアリングはコミュニケーション能力だ」という例を挙げましたが、知識や概念で言う最もらしいことというのは一見正しそうに見えますが、事実を見ていない単なる知識なので実際は役立たないことも多い。だから相談し、対話するに値する相手かどうかを主体的に判断できる自分であることが大事なのです。理屈は言うけれど具体例が出てこないかたの話しは空しい。具体例も本や新聞からの引用ではなくて、自分が実際に経験した具体例であることが大事です。その具体例から学んだことなら聞く価値はあるでしょう。
今回のコラムは前回のコラム264号と前々回のコラム263号を補足する内容を具体的に説明してみました。実際には受け身で相談に行って、最もらしいけれど役立たない一般的な助言をもらってくることも多いと思います。その無駄な相談の責任は残念ながら自分にある。世の中やはり甘くないのです。