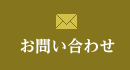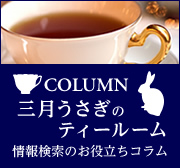情報検索コラム
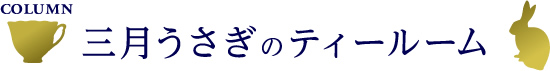
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
ビジネス支援を受ける -溺れないためには藁をつかまない-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
拙著『社会人・学生のための情報検索入門』執筆当時はビジネス支援図書館について、いろんな面から関わっていました。さらに書籍の執筆は私自身が事務所を開業して間もない時期でもあり、いくつかのビジネス支援を受けた経験もあります。ここ1年半の当コラムで書籍執筆時の様々経験を書いた機会に、前回のコラム262号ではビジネス支援について「情報」の面から書きました。今回のコラムではビジネス支援について「支援を行うひと」の面から書きたいと思います。
既に260回以上書いているこの情報検索コラムはサーチャーの仕事について様々に書いているため、サーチャーを目指すかたも読んでくださっているようです。特にサーチャーとして独立して仕事をしたい、つまり開業(フリーランス)したいと思っているかたも少なくないようです。またセミナーや講演などの質疑でも、独立開業を考えていると思われるかたから質疑を頂くこともあります。
そのようなことも含めて、ご自分で開業を考えているかたへビジネス支援を受けるときの注意点を書きます。良いビジネス支援を受けるための参考にして頂ければ幸いです。今回のコラムは最初に残念なビジネス支援者の例をいくつか書いたうえで、それらの残念な例に対比させるかたちで良いビジネス支援者の例を書きました。良いビジネス支援者は一見すると「普通」なのですが、この普通さが実は大事です。これは残念な例を踏まえたうえで良い例(普通)を対比すると理解しやすいかなと思い、残念な例 → 良い例 の順で書いてみました。かなり長いコラムになりました。そのつもりでお読み頂ければと思います。
残念なビジネス支援者1:仕事の基本を身につけていない
まずは残念な話しから始めますが、私が開業して間もない頃に接したビジネス支援者の方たちは、仕事の基本を身につけていないかたが多かったです。
まずひとつめの例。ここ1年半の当コラムで書籍執筆時の様々経験を書いてきた中で、出版社の対応の不備をいくつも書きましたが、この出版社はビジネス支援図書館推進協議会の理事のひとりです。ビジネス支援図書館推進協議会のホームページを見ると、大変に立派な活動をしています。しかしながらビジネス支援を行うかた自身のビジネスの仕事ぶりが立派かというと、残念ながら違いました。
具体的に列挙します。既にコラムにもいくつか書きましたが、仕事相手である私(味岡)へのレスポンスを含めた対応が不適切でした。例えば執筆費用の分担について問合せても返事が無く、お会いしたときに面と向かって確認したら「出版社は執筆費用は負担しない」との返事でした。著作物使用時の著作権処理について確認したときは全く無く無回答。しかたがないので全て自分で処理しましたが、出版社が対応しなければいけないものがいくつもあったことはコラム255号に書きました。しかも製版時のページの割付が指示通りではなく、他かたの著作物を仮使用した箇所の差し替えの指示も無視されました。そしてそもそも原稿を送っても編集者からは全く返答が無い。数か月後に返事が来た頃には検索例に使った検索システムや検索画面が既にアップデートされてしまって、ほぼ全ての検索例が作り直しになりました。これらは全て仕事相手である私への対応が不適切であった例です。
事務処理も不手際が多かった。何をやらせても不備があって、出版契約書には私の名前ではなく、他の本の著者の名前が書かれていたので作り直してもらいました。出版契約書を送ってくるときも、送付文書などの書類を付けて送ってくるのではなく、キャラクター入りのメモ紙(!)に手書きしたメモがついてきました。しかも本は発行予定日に発行されなかったので出版社に確認したところ、他の本を発行したため遅れるとのことでした。よって奥付の発行日は「2009/4/30」ですが、実際の発行は5月下旬でした。余談ですが、奥付の発行日と実際の発行日(公知日)はこのように相違するので、奥付に記載される発行日は特許の無効資料調査の公知日の証明に使えないのです。さらに最初に刷ったものは奥付けの印刷にプリントミスがあって(書名が違っていた)、全部数刷り直し。大変に無駄なコストだと思うのですが、よくこれで会社がもつなと思いました。そして出版後、出版社のウェブページに掲載された本の紹介は他の本の紹介でした。これも出版社へ連絡して直してもらいました。
他にも挙げていけばキリがないのでこのあたりで止めますが、とにかく何をやらせても満足にできない。ミスや不備が発生しても隠せるものは隠す。そして隠せなかった場合や、ミスを指摘されたときもゴメンナサイが言えない。
例えば私たちフリーランサーがミスだらけの仕事をして、仕事の依頼者への返答が遅かったり不適切だったりしたなら信頼してもらえません。信頼関係ができなければ仕事を継続して依頼しえもらえません。つまりビジネスはできない。仕事はどんなに注意してもミスが発生することはあるのですが、その場合も正直に謝罪して誠実に修正し、再発防止策を講じる。これらはカッコ悪いことを行うことでもあるのですが、このカッコ悪いことをキチンと行えるようにならないと相手に信用してもらえないし、自分を信じることもできないわけで、私はこれがビジネスの大事な基本のひとつだと思っています。信頼関係の無いところに良い仕事は生まれません。これから事業を開始しょうという最初の段階では仕事の基本も身につける必要があります。あなたがビジネスでの信頼関係を築きたいのであれば、仕事の基本が身についていないビジネス支援者の支援を受けることはお勧めしません。
出版社のかたに限らず図書館のかたも残念なかたが多かったです。参考としてひとつだけ書くと、ビジネス支援を行う図書館のかたへデータベース検索の講習を2回にわたってしたとき(コラム218号参照)のことです。1回目は講義、翌月の2回目は検索実習でした。検索実習は1回目の講義での質疑や感想を含めたレポートを提出してもらって、このレポートを踏まえて例題を作るつもりでした。ところがこのレポートが1カ月経っても届かない。あまりに遅いので図書館の講習開催の責任者へレポート提出の催促したところ、受講者全員のレポートを紛失してしまったとのことでした。これも無責任な仕事ぶりですが、私が催促しなかったなら紛失したことは知らせてくれなかった。紛失を知らせて謝罪して、ミスに迅速に善処するということができない。結局、受講者全員にレポートを再提出してもらいましたが、1か月後の検索実習に間に合うような対応はしてもらえませんでした。
これは実際にビジネス支援を行う図書館での例なのですが、以前のコラム198号「特許情報や調査から見た起業、ビジネス -支援する能力-」や前回のコラム262号「仕事に必要な情報とビジネス支援」に書いたように、情報要求者に必要なズバリの情報が図書館で何も問題無く見つけられることは少ないのです。必ず上手くいかないことがある。ときには図書館員の情報要求内容への理解不足が露呈することもあるし、図書館での情報収集の不十分さが発覚することもある。そんな様々に不備が発生する課程で分からないことは正直に分からないと言い、できなかったことは正直に伝え、間違えたことは謝罪して善処し、できるだけ相手のニーズに応える。そのためには勇気を持って誠実、正直、丁寧に仕事するしかない。と、ここまで書けば分かると思いますが、レポートを紛失するという責任感の無さ、それを講師へ伝えないという不正直さ、次回の検索実習に間に合うように処置できないという仕事のできなさ。このような仕事ぶりの図書館に誠実なビジネス支援をしてもらえるとは思わないでしょう。
残念なビジネス支援者2:相手を尊重しない
上の項ではビジネス支援図書館を中心に書きましたが、一般的な公的機関でのビジネス支援者にも残念な例が多かったです。私が開業した頃、公的機関でビジネス支援を担当しているかたからビジネスプランコンテストへの参加依頼を頂きました。このかたは私が公共の特許情報室に勤務していた頃から面識があるかたでした。私としてはビジネスプランコンテスト事業への協力というかたちで参加することにしました。ビジネスプランコンテストに参加する場合、コンテストに向けてプレゼンテーションのブラシュアップが行われます。具体的に言うと、参加者側がプレゼン用のパワーポイントを作成し、そのパワーポイントをビジネスプランコンテスト担当者数名で検討して修正などを行い、より良い発表内容になるようにします。
ブラシュアップは参加者別に日時が指定されます。参加者は指定された時間に指定された場所、例えば開催機関の会議室などへ行き、パワーポイントでプレゼンを行います。私が指定された日時にブラシュアップを受けに行ったときのことです。私が指定された時間になったのですが待たされました。そのときビジネスプランコンテスト担当の職員のかたが私に「まだ前のかたがまだ終らないの。すごく一生懸命な説明で長引いちゃってるの」と言ってウフフッと笑うのです。ずいぶん失礼だなと思いました。私に時間が遅れていることを説明してくれたのは良いと思います。でも説明にあたって前のかたのビジネスプランへの敬意が感じられませんでした。
というわけで開催担当者への疑問を感じつつ、15分くらい待たされた後で私のプレゼンの検討が始まりました。ブラシュアップを担当するかたは2名でした。1名はビジネスプランコンテスト開催担当のリーダー、もう1名は外部から来てくれている税理士さん(ビジネスプランは収支に直結する)でした。このときの開催担当のリーダーのかたの服装ですが、毛玉だらけのセーターにサンダル履きでした。これは仕事の基本ができていないという点でもNGなのですが、仕事相手に失礼な服装です。ビジネスプランコンテスト参加者には、このような服装で接しても構わないという意識を持っているのだなと思いました。ブラシュアップを受けに行った私は当然ながらスーツです。税理士のかたもスーツでした。
このときのブラッシュアップでのアドバイスは残念ながら参考になりませんでした。税理士のかたからのアドバイスは、話し方が早すぎるとか、専門用語は使わないほうが良いなど参考になるアドバイスでした。それに対して開催担当のリーダーのかたは、特許やデータベース、調査などについて良く知らないにも関わらず自分の知識をやたら披露するかたでした。一般的にビジネスプランコンテストに参加するレベルの起業者ならば、参加者は自分が行おうとするビジネスの専門分野には詳しい。それに対して開催担当者は各ビジネスプランの専門分野に同じくらい詳しいわけではないのが当たり前です。だからまずはビジネスプランの専門的な内容を勉強するという姿勢になるはずです。専門的な内容を理解できなければ適切なアドバイスはできないでしょう。専門的な内容を勉強するという意識があるならば、そこにはコンテスト参加者への敬意や尊重があるはずで、敬意や尊重があるならば毛玉だらけのセーターにサンダル履きという服装はできないだろうと。そういいうことです。
図書館での例を挙げます。上の項にも書いたビジネス支援を行う図書館のかたへデータベース検索の講習に先立って、講習開催の責任者かたから図書館でのビジネス支援状況の説明を受けたときのことです。データベースの利用状況が印刷された資料を頂きましたが、資料の用紙にはミスコピーの裏紙が使われていました。図書館としては省資源への意識やコスト意識をアピールしたかったのかもしれません。しかしビジネスの面から見た場合、次の2点でNG行為です。ひとつめの点は「守秘」。ミスコピーの内容が外部(この場合は私、味岡)へ知られてしまうことです。守秘の意識が強い会社では、外部へ渡す資料に裏紙は使わないものです。ふたつめの点は「失礼」。私に限らず外部へ渡す資料に裏紙を使うのは失礼です。資料に限らず、外部へ渡すものは適切にコストをかけて渡すことで相手を尊重していることを示す。その気持ちが伝わることで信頼関係につながって、良い仕事関係が築かれるものだと思います。
似た例をもう一つ挙げると、先に書いたビジネスプランコンテストのときも、ブラシュアップを受けに行ったときに開催担当のリーダーのかたへ名刺をお渡ししたのですが、私の名刺は印刷所で作ってもらったものでした。開催担当のリーダーのかたは名刺を受け取って「こんな大企業みたいな名刺は作らなくて良い。名刺なんてカレンダーの裏に刷ったって良いんだよ」と言いました。私のコスト意識の無さを指摘したのだと思いますが、とんでもないです。上にも書いたとおり、仕事相手にお渡しするものは適切にコストをかけて相手への敬意や誠意を示すものだと思います。無駄に見栄を張る必要はありませんが、少なくともカレンダーの裏に印刷するなど問題外です、まぁカレンダーの裏というのは言葉の綾だとは思いますが。でも実際、大学で学生の起業支援を担当する先生で、コピー用紙で名刺を作っていたかたがいました。名刺交換のときポケットからグチャグチャのコピー用紙の名刺を取り出して皺を伸ばしながら「ちょっと経費削減で・・・」と言いながら私にくださいましたが、それを横で見ていた学生の皆さんがズッコケていました。ちなみに学生さんたちから頂いた名刺は名刺用紙に印刷されたもので、名刺用のテンプレートを使って自作したものでした。学生さんとしては適切なコストのかけかただと思います。もしも印刷会社で作った名刺を使っていたなら、学生としては不相応なお金のかけかたでしょう。
良いビジネス支援者
上の2つの項で残念な例ばかり書いてしまったのは、それだけ残念なビジネス支援者が多いということです。私が接した多くのビジネス支援者のうち「このかたはプロフェッショナルなビジネス支援ができるかただな」と思ったかたを紹介します。
このかたはじつは有名なかたです。このコラムではこのかた個人を紹介するのが目的ではではなく良い支援者の特長を説明するのが目的なのでお名前は伏せますが、メディアにも様々に出ていらっしゃいますので、お名前を出せばご存じのかたも多いと思います。
このかたを仮にK氏とします。メディアでのK氏の紹介などを読むと、K氏は銀行のM&A担当等を経て創業支援の仕事に向かわれたとのことです。その過程で銀行は退職なさって会社を立ち上げて中小企業支援施設の運営のに携わってきたとのことです。K氏について大変簡単に紹介してしまいましたが、K氏は起業に限らず事業支援のプロです。K氏とは自治体が行うビジネス支援関連の会議で、ご一緒する機会がありました。その会議で私の仕事が情報検索や調査だということを理解してくださったようです。この会議があってからしばらくしたときのことです。K氏に新規事業でのアイディアを相談にいったかたが情報(データ)が必要になって、K氏が相談者に私を紹介してくださいました。情報要求内容については守秘に反するのでここに具体的に書けないのですが、特定の問題を解決するというアイディアでの新規事業で融資を受けるにあたって、特定の問題の発生状況が分かるデータが必要になったとのことでした。サーチャーが情報入手を助けてくれる、という紹介のしかたをしてくれたようです。
この相談者のかたの求める調査が終って間もないときに、出張でK氏のオフィスの近くへ行く機会がありました。出張の仕事が終った後でK氏のオフィスへ、仕事を紹介してくれたお礼と無事に情報提供できた報告をしに行きました。簡単なお礼と報告なので特に連絡などはせず、もしもK氏がオフィスにご在席ならば挨拶を、と思っての訪問でした。受付のかたは私を起業の相談者だと思って取り次いでくださったようです。だからK氏は私が来訪したとは思わずに、相談者が来たときに対応する態度で「はい、何でしょうか?」と出てきてくれたのですが、その言葉や態度は私が接してきたビジネス支援者とは全く違いました。相談者に対して丁寧に接する気持ちが見て取れました。服装はスーツ。相手が相談者ではなく私だと分かると、目を見てキチンと挨拶してくれました。このようなかたなら信頼するに値します。誠実に対応してくれるでしょう。
さて、このK氏に相談したうえで私のところへ情報入手の相談にきたかたは最初に「K先生から味岡さんを紹介してもらいました」と経緯を説明してくれました。このように経緯を説明するのは当たり前のように思うかもしれませんが、じつはなかなかキチンと説明できないかたが多いのです。K氏に指導してもらっているかたは、ビジネスの基本も身についているなと思いました。
K氏の服装がスーツというのも当たり前なのですが、上に書いた残念なビジネス支援者の例を見て頂くと分かるとおり、当たり前のことができないビジネス支援者もいます。他にも残寝な服装の例として、ビジネス支援を行う図書館の責任者のかたはいつも黒のタートルネックを着ていました。たぶんスティーブ・ジョブズ(米Apple社の共同創業者の一人。いつも黒のタートルネックを着ていた)のマネだと思います。ジョブズならビジネスウェアとして通用するかもせれませんが、一般人が同じことをしても滑稽なだけです。特にスーツでなくても構わないけれど、相手に失礼のないTPOをわきまえた服装は仕事の基本でしょう。外見は内面を表すものです。
ちなみに私がビジネスプランコンテストに参加してブラッシュアップのときに来てくれていたスーツ着用の税理士のかたは、参加者に対して指導的な態度をとるかたではありましたが知ったかぶりをするようなことはありませんでした。私のビジネスプランに対しては、特許や情報の専門的なことは分からない面もあるけれど、ご自分の分かる範囲でアドバイスをくださいました。だからこそ話し方が早すぎると理解が追いつかないとか、この用語は専門用語だから分からないひとが多いとか、率直なアドバイスが参考になりました。
溺れたくなければ藁はつかまない
起業、創業、開業など言葉は様々に使われますが、いずれにしても事業を新たに始めたばかりのときは不安が大きいのが普通です。どうしたらやっていけるのか不安だらけで、少しでも早く安心したくて藁にもすがる気持ちになるものだと思います。でも藁、つまり頼りないものをつかんでも溺れるだけです。つかもうとする時間とエネルギーは無駄になります。不安で心配だとは思いますが落ち着いて、藁ではなく救命具となるビジネス支援者を探しましょう。
ビジネス支援者を選ぶとき、私がお勧めするのは相談者であるアナタから学ぼうという意識をもったビジネス支援者に相談することです。コンサルタントのかたなどとお話しすると、まずは様々な業種について一通り学んでから、IT系、医療系など専門別に学んでコンサルなさるようです。でも例えばアナタがIT分野で起業されるとき、コンサルタントに限らずIT分野に詳しいかたに相談したとしても、アナタのアイディアや予定事業の中には知らないことや分からないことがあるはずです。まして専門外ならなおさらです。様々な業種について一通り学んだだけではアナタの起業内容に分からないことが何もないビジネス支援者などいないはずです。特に起業にあたっては、他のひとが考えていいないような新規なアイディアを持っている場合も多いでしょう。
この点は私たち特許サーチャーと似ていて、特許サーチャーは化学、機械、通信など様々な技術分野をそれぞれ専門としていることがあります。でも調査依頼を頂いたときは、たとえ自分の専門分野の調査だとしても自分が既に持っている知識だけで調査を開始できることは、まずありません。必ず調査が開始できる状態まで、その調査内容の技術について勉強します。そして調査中も分からないことがあれば必ず確認しながら調査を進めます。
このような特許サーチャーとしての経験から言っても、まずは学ぶところから始めるビジネス支援者でないと適切なアドバイスはできないと思います。最初からアナタを指導しようという意識を持って接してくるビジネス支援者は避けたほうが良いでしょう。普通に考えると開業時は分からないことだらけだから、いろいろと教えてくれてるヒトに頼りたいと思うかもしれませんが、まずは「教える」の前に「学ぶ」ができるヒトを選んでください。「学ぶ」ができるかたなら仕事の基本も身についているかたが多いと思います。事業を進めながら、仕事のしかたも学んでいくものなので、なるべく良い仕事ぶりに接することも大事です。また学ぶという意識があるということは、自分が分からないことや知識不足のことに正直に向き合えるということです。このような正直さがあるなら不誠実な支援はしないと思います。
大変長いコラムになりました。読んでくださって有難うございます。いろいろと具体例を書いたので、少しでも参考になる箇所があれば幸いです。
書いていて思ったのですが、コピー用紙で名刺を作っていた先生の指導を受けていた学生さんは、キチンと名刺用紙とテンプレートで作った名刺を使っていたんですよね。あの先生のダメなところを学んでいなかったのは幸いだったかなとも思いました。ついでに書いてしまうと、公共の特許情報室に勤務していた頃にことです。市内に大学の工学部がある関係で、工学は特許と関連が深いため大学のかたたちが情報室にいらっしゃることがありました。で、率直に言ってしまうと、大学の職員のかたがたよりも学生さんたちのほうが優秀だなと思いました。優秀というのは学問的な面ではなくて、挨拶がちゃんとできるとか、相手の話しを聞くとか、相手に分かるように説明するなど、対人コミュニケーションや社会性の面です。なんだか学生さんたちのほうがはるかに大人でした。社会性があって優秀な学生さんは企業へ行ってしまうから大学には残っていないのか、それとも大学という閉じた世界にいると社会性が不要になっていってしまうのか、理由は分からないのですが。そんなことも思い出しながら書いたコラムでした。