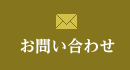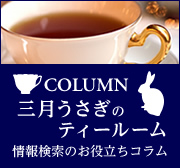情報検索コラム
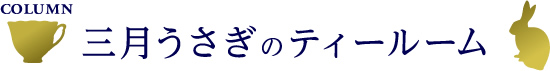
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
ビジネス支援を受ける -ビジネス支援 Show のしくみを知る-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
この情報検索コラムはサーチャーの仕事について様々に書いているため、サーチャーを目指すかたも読んでくださっているようです。なかにはサーチャーとして独立して仕事をしたい、つまり開業(フリーランス)したいと思っているかたもいらっしゃるようです。またセミナーや講演などの質疑でも、独立開業を考えていると思われるかたから質疑を頂くこともあります。そのような経緯から書いた前回のコラム263号「ビジネス支援を受ける -溺れないためには藁をつかまない-」に続いて、今回のコラムもご自分で開業を考えているかたへ、ビジネス支援を受けるときの注意点を書きます。ビジネス支援を受けるための参考にして頂ければ幸いです。
Action が無くて Show のビジネス支援
以前、特許情報業界のかたが書かれたコラムを読んで "公共機関のプロジェクトって、どこでも同じ経緯をたどるんだな" と妙に納得したことがあります(※参考URL参照)。
このコラムの中で筆者のかたは「頻繁に、同じような政策課題に対し若干名称が変わっただけのプロジェクトが現れては消えてゆく事を繰り返しているように感じていた」と書かれていて、さらにPDCAサイクル(Plan:計画 -Do:実行-Check:評価-Action:改善)に言及されたうえで「国や公共団体、そこからの影響が強いアカデミアでは企画偏重、箱物行政が先行しがちであるが、(ある意味厄介な)CAが伴わない故に貫徹しない効果不明なプロジェクトが多くないだろうか。」との指摘がありますが、私も実際まさにそのとおりだと思うので(引用出典:※参考URLから)。
以前のコラム196号「特許情報や調査から見た起業、ビジネス -支援する側を見る-」で次のように書きました。
---------------コラム196号から抜粋、( )内は補足---------------
(公的機関におけるビジネスの)支援に関する会議にいくつも参加させられましたが、大がかりで、何回も会議を開いて、何か月も行うのですが、成果や結果が出せたものは一つもないです。(中略)少なくとも私の参加した会議では、何も結果がでないまま次の年度になれば事業も変わって担当者も変わって「会議しました」で終わってしまう。この繰り返しでした。
--------------------------------以上、抜粋----------------------------
というわけで Plan:計画 -Do:実行 は大がかりに行うけれど「CAが伴わない故に貫徹しない効果不明なプロジェクト」を私なりにいっぱい見てきました。ここで「CAが伴わない」と書かれていたことについて "あぁそういえば公共機関のプロジェクトって、 A(Action)じゃなくて S(Show)なんだよね" と思いました。次のよりよい事業の Plan のためにサイクルを回すという思考は無いので。つまり「やりました=このように予算を使いました」と見せて(Show)お終い。
Show のための Check
PDCAサイクルのほかに、現在ではO:Observe(観察)-O:Orient(方向づけ)-D:Decide(意思決定)-A:Act(行動)ループも用いられると思いますが、PDCAサイクルもOODAループも4つめの「A」は次へつなげるために行います。ところが最後を「Show」にすると次につながらない。本当はよりよい仕事につなげなければいけないのですが、見せて(Show)お終いという仕事のしかただと、当然ながら「A」に先立つ「C」の意味も変わります。
例えば、これからビジネス支援を行おうとする市立図書館の会議に協力したときのことです。新たビジネス支援をに行うために、その図書館では特別な予算を国から支給されていました。だから「このように予算を使いました」と国に見せる(Show)ための報告書を作成する必要があります。ビジネス支援という事業は Plan:計画と Do:実行 です。ただし Check:評価はこの報告書に載せるために行う。ということであると、どういう Check になるか。
本来、より良いビジネス支援につなげるための Check なら、改善すべき点がわかるような Check 方法を考えるでしょう。また本当に効果があったかどうか検証できるような方法を考えるはずです。会議では報告書に載せるための Check 方法の検討も行いました。単純な私は次なる「A」のための「C」だと思って、Check 方法をいろいろと提案しました。
この会議の参加者は全部で7名でした。まず当然ながらこの市立図書館のビジネス支援担当者。そして大学の図書館情報学の先生が会議の議長でした。以下、市の商工労働部の担当者。市内にある大学図書館の館長。またこの市立図書館ではビジネス支援と同時に多文化対応にも取り組むということで、大学で多文化対応・多言語対応を専門とする先生。そして市内でデザイン関連の事業で起業したかたが起業者代表として参加。私はビジネス情報関連を担当しました。
さて、この Check 方法の検討会議で市の商工労働部の担当者は「ビジネス関連の本がどの程度利用されたかの検証が必要ではないか」と発言されました。すると市立図書館のビジネス支援担当者かたが「本の利用統計はとれるけれど、ビジネス用の本を拾い出して統計をとるのは難しい」と回答しました。そこで私が「個々の本の利用状況ではなくて、例えばNDC(図書館の本の分類)の3門(社会科学)、4門(自然科学)、5門(技術)、6門(産業)の本全体の利用率を調べて、ビジネス支援をしていない市内の他の図書館(分館)の3門、4門、5門、6門の本の利用率と比較すれば、産業や経済関連の本がよく利用されているかどうか分かるのではないか」と提案しました。市の商工労働部の担当者は「あぁそういう方法もありますね」と言ってくれて、市立図書館のビジネス支援担当者かたは「検討します」とのことでした。この方法なら統計はとれるはずなのですが、出来上がった報告書にはそのようなデータは全くありませんでした。
もしも実際に3門、4門、5門、6門の本の利用率を調べたなら、たぶんそんなに目立って利用が多いということはなかったはずです。本来の「A」につなげる Check ならば「利用されていない」という事実が分かることが大事で、そこから次の Plan を考える。でも Show のための Check は良い結果を見せないといけないので、利用されていないという事実は報告に値しないのだと思います。
またビジネス支援を行う理由(国に予算請求をした理由)として「市内の起業率は低いため、経済の活性化として起業を推進する」という趣旨が当初の説明に書かれていました。そこで私が「市内の起業率が上がったかどうかの検証が必要ですよね」と言ったところ、大学図書館の館長のかたや市の商工労働部の担当者のかたも「そうですね」という顔でうなずいてくれたのですが、議長の図書館情報学の先生から「それはパラメータの設定が難しいので」と拒否されてしまいました。図書館情報学の先生は市立図書館側の立場のかたです。図書館情報学の先生も、市立図書館のビジネス支援担当者かたも頭の良いかたなので、出来ない理由を即座に返してきます。単純な私は、当初の目的が達せられたかどうか確認しないといけないでしょう、だったら検証可能にパラメータの設定をすれば良いじゃないか。と思うのですが、このとき既に "このかたたちは本当に起業支援をしようとしているのではなくて、単にキレイな報告書を作りたいだけなんだな" と気付いていたので、それ以上は反論しませんでした。これも実際に起業率を検証したなら、そんなに効果は無かったはずです。そして効果が無かったのは何故なのか考えるのが大事なんですけど。
この流れでもう一つ書くと、ビジネス支援と同時に多文化対応にも取り組むということで、当初の説明では市内在住の外国人のかたの様々な問題解決に図書館を役立ててもらうとのことでした。ところが報告書には問題解決ができたかどうかは全く書かれていなくて、外国人のかたへの読み物(小説や絵本)提供が喜ばれたという報告になっていました。当初の目的とはズレているのですが、本当にキレイな報告しか書いてないなと思いました。
Show のためのビジネス支援
いかに良い「Show」をするか、つまり「私たちはこんなふうにビジネス支援をしています」と見せるのが目的であって、起業者や事業者へより良い支援を行おうという意識が希薄なのであれば、前回のコラム263号で書いたような、残念なビジネス支援者が多いことも理解できるかと思います。
公的機関の意識を別の例で書いてみます。私が公共の特許情報室に勤務していたときのことです。
特許情報室では市内の企業のかたが特許検索や技術文献検索を利用しにいらっしゃいます。私たち職員は特許検索や文献検索の案内をします。調査したい内容を伺って、検索式を考えて、データベースの利用方法を案内して、実際に検索してもらいます。検索するのは利用者のかた自身ではあるものの、検索式を考える(提案する)のは職員です。利用者のかたの調査テーマによっては上手に検索案内できないこともあります。上手く情報入手できなかったときは、やはり悩む。検索記録を見ながら、どうしたら良かったのか考え込むのですが、これが市役所から出向してきた上司には鬱陶しく見えたようです。あるとき上司に言われました。「上手くいかなかったのを自分の責任とか思わずに、もっと仕事を楽しめば良い」と。
とんでもないです。当時のデータベース検索料は従量制が主流で、今よりも高価でした。上手くいかなかった検索の使用料も利用者のかたが負担します。上手くいかなかった検索に料金を払ってもらって、申し訳なく思うのは当たり前ではないかと。しかも検索での情報入手が上手くいったっかどうかは、企業内での研究開発に影響する。ということは企業の損益に関わるわけで、そこにも私たちの責任を感じる。だから「楽しめば良い」なんて思えない。でも上司には嫌がられました。気楽にやるのが全くいけないとは言いませんが、少なくとも責任はあるはずで、この責任の感じ方が公的機関では薄いのではないかとも思いました。
だから公的なビジネス支援も、あまり支援相手への責任などを思いつめない。そしてキレイな報告をする。そんな感じかな、と思います。なかには熱心に取り組んでいる担当者のかたもいるとは思いますが、私が見てきたかぎりでは起業者や事業者へより良い支援を行おうという意識や責任感は薄いかたが多いように思います。支援の成果は出なくても給料は出る。乱暴な言い方ですが、そういうことではないでしょうか。
ビジネス支援を受けるヒント
そんなビジネス支援を受けるということであれば、大事なことのひとつは自分の必要な支援は何なのかを明確にすることだと思います。必要なのがお金(融資)なのか、起業の手順なのか、顧客開拓のためのDM用リスト作成なのか、事業のための専門知識や技術なのか、等々。そのうえで相談に行けば、対応してくれた相手が前回のコラム263号で書いたような残念なビジネス支援者かどうか、また今回のコラムに書いたような「ビジネス支援をしてます」と見せる(Show)だけの支援者かどうかが判断できるのではないかと思います。要は受け身で相談に行かないこと、自分の側に主体性を持つことだと思います。この支援者はダメだと判断したなら、関わらないほうが良いです。
※参考URL
責任論(2024.08.21 /佐々木剛史)株式会社発明通信社 コラム「イーグルアイ No.4」
https://www.hatsumei.co.jp/column/e-4/
※このコラムで引用した箇所がどのような文脈の中で書かれていたか、原文でご確認頂ければ幸いです。
今回のコラムで、上手く検索できなかったときは検索記録を見ながら、どうしたら良かったのか考え込むと書きましたが、それは今も同じです。
一年くらい前に、普段は使わない無料の検索システムを使って文献検索しなければいけなくなったことがありました。使い慣れていないうえ、無料なので普段使っている有料の検索システムでは使える機能が使えない。結果としては良い文献が見つけられたので、お客様には喜んでもらえたのですが、検索そのものは上手にできたとはいえませんでした。
このときも調査報告を納品した後、検索記録を見ながら、どうしたら良かったか考えました。だって上手に検索できなくて悔しかったから。で、別の作業をしているときに、ふと「こうしたらできたよね、きっと」と思いつきました。でも普段は使わない検索システムなので、その方法を使う機会は無さそうだなと思っていました。ところが先日、その検索システムとは別の無料の検索システムを使う機会がありました。
その検索システムで検索するのは初めてで、しかもやはり有料の検索システムでは使える機能が使えない。そこで「こうしたらできたよね」と思っていた方法を試したら、できました(!)。PDCAが回って、前に進めました。だからやはり検証(Check)って大事です。検索を検証して考え込んでいるサーチャーを見ると鬱陶しい・・・かもしれませんが、大事なステップなので、あまり嫌がらないで暖かく見守ってほしいです。はい。
※なお、この検索方法は改めてこのコラムで紹介したいと思っています。