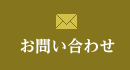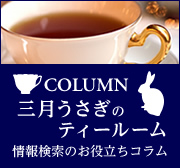情報検索コラム
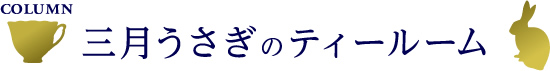
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
仕事に必要な情報とビジネス支援
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
前回までのコラムで、書籍『社会人・学生のための情報検索入門』執筆の経験をもとに情報の信頼性判断について様々に書きました。この書籍は2009年発行ですが、この書籍の執筆依頼を頂いたきっかけは、書籍発行元の出版社が、ビジネス支援図書館推進協議会の理事だったことによるものです。私は図書館司書の資格があり、企業の図書室での勤務経験と公共図書館での勤務経験があり、さらにサーチャー資格を得て公共の特許情報室でも勤務したうえで個人事務所を開業しました。そんな経歴だったため開業(2003年)直後の数年はビジネス支援図書館関連の講習会の講師の依頼を頂いたり、ビジネス支援を行おうとする図書館の事業推進会議への参加の要請を頂いたりしました。これらのうち、ビジネス支援図書館協議会が主催する講習会のデータベース検索の講師を務めた関係から、ビジネス支援図書館推進協議会の理事だった出版社(ひつじ書房)から情報検索の本の執筆依頼を頂いたという経緯があります。
というわけで書籍執筆当時はビジネス支援図書館について、いろんな面から関わっていました。ここ1年半の当コラムで書籍執筆時の様々経験を書いた機会に、ビジネス支援図書館を中心にビジネス支援について「情報」の面から書いておこうと思います。
仕事に必要な情報とビジネス支援図書館
ビジネス支援図書館推進協議会の組織紹介のページには次のとおり書いてあります。
「図書館の持つ冊子情報源やデータベース等活用すれば、市民の起業とNPOや SOHOを含むマイクロビジネス等の創業を喚起し、また、地域経済の担い手である中小企業やベンチャービジネスの支援を行うことが可能となります。」(2025年3月参照:https://www.business-library.jp/aboutbl-2/)
実際、私がビジネス支援図書館を行おうとする図書館のお話しを伺うと、図書館の蔵書の中でもNDC(日本十進分類)の3門(社会科学:政治、法律、経済、統計など)、4門(自然科学:数学、理学、医学)、5門(技術:工学、工業、家政学)、6門(産業:農林水産業、商業、運輸、通信)を充実させて、新聞記事検索や文献検索のデータベースも導入して、ビジネスに必要な情報を提したいということでした。現在のビジネス支援図書館推進協議会のウェブページを見ても、この頃から考え方は変わっていないようです。
ここで起業に限らず、実際に仕事に必要な情報はどんな情報なのか、いくつか具体例を挙げます。
例1:工業デザイン
私の書籍での調査例に引用し、コラム258号でも紹介した「3.6.3 図書館での調査例:6~7世紀の美術品(装身具)の図版を探す」で、イタリア・ランゴバルド(ロンバルディア)の6~7世紀の美術品の図版を探した例は、工業デザイナーのかたからの依頼でした。この調査に使った本はNDC7門(芸術、美術)とNDC2門(歴史)のヨーロッパの歴史の本です。3門、4門、5門、6門の本は全く使いません
でした。
例2:建設会社
機会があって建設会社の図書室を見せていただいたことがあります。図書室なのでNDC順に本が並んでいるのですが、NDC1門(哲学・宗教)の棚に様々な宗教の辞典・事典類がずらりと並んでいました。一般の書店でも見かけない、かなりの充実ぶりでした。思わず「建設会社の図書室にしては珍しい本が充実していますね」と言ったら、案内してくださったかたが「え?そうですか」と意外そうな顔をなさって「宗教に関係する建設の場合は、その宗教に関する知識が必要なので」と当たり前のように説明してくれました。私は自分の思い至らなさを恥じましたが、このNDC1門(哲学・宗教)も3門、4門、5門、6門から外れているけれど、仕事に必要な情報です。
例3:パソコンディスプレイの統計
ならばNDCの3門、4門、5門、6門に属する統計データは仕事に使えるはず、と思いたいところです。でも実際に統計データを調べてみると分かりますが、一般に公開される統計類は自分に必要なデータとはズレていたり、数字が大きすぎたり小さすぎたりで、そのまま使えるズバリのデータが見つかる事は稀です。実例としてコラム193号で「パソコンのディスプレイのサイズ別の売り上げ統計」を探した例を紹介しました。この場合、「パソコンの売り上げ統計」(←大雑把すぎる)や、「ディスプレイ限定のサイズ別出荷統計」(←出荷なので販売とは相違する)でした。これは特殊な例ではなくて、一般に統計データを探すとこのようなことになりがちなのです。この場合は一般公開されている統計データからは見つからなくて、複数の通販サイトの売上ランキングなどを使いながら、目的に近いデータを独自に集計して、調査依頼者へレポートしました。この場合は独自のデータ採集と集計なので図書館を使う事さえ必要なしです。というわけなので、単に統計データを例にとってもビジネス支援図書館が想定している「図書館の持つ冊子情報源やデータベース等活用」では対応できない面が多々あります。
例4:蕎麦の打ち方
ある料理雑誌で蕎麦屋を開業したかたの紹介がありました。このかたは開業に先立って、蕎麦の打ち方を研究されたとのことです。その研究を国立国会図書館に行って本や文献を網羅的に入手して読み込んで、独自に研究して自分の蕎麦の打ち方を考えていったと紹介されていました。雑誌の記事なので、どの程度正確に紹介されているかは分かりませんが、今の時代、蕎麦の打ち方は動画を含めてインターネットで様々に入手できるのに、国立国会図書館の本や文献で網羅的に情報収集して研究したというのはユニークだなと思いました。蕎麦の打ち方ならNDC5門(技術:工学、工業、家政学)に属するので、ビジネス支援図書館の思想に合致しそうですが、この例のポイントは「国立国会図書館で情報収集した」という点にあります。コラム217号「社会に出てから必要になる知識や情報を図書館で得られる…か?」で詳しくかきましたが、身近な公共図書館で仕事に使う情報を探した場合、断片的で不十分な情報しか得られないことが多いのです。蕎麦の打ち方にしても、このかたは本や文献を網羅的に入手して独自に研究したかったわけです。ビジネス支援図書館に取り組んでいる公共図書館では、このようなニーズには応えられない。ビジネス支援図書館が想定している起業や創業について、どんな業種で起業、創業しても応じられるだけの網羅的な情報を一般的な公共図書館で所蔵するのは予算的にも規模的にも無理です。国内で可能なのは国立国会図書館、そして各専門に応じた大学図書館や専門図書館でしょう。文献については公共図書館が入手支援しなくても、国会図書館の文献は自分のパソコンで検索して直接取り寄せが可能です。残念ながらビジネス支援図書館の活躍する場は無い場合が多いのです。
例5:開業/起業を紹介した本や雑誌記事
図書館なら様々な開業例/起業例の本や雑誌記事が所蔵されています。これなら起業しようとするかたに役立ててもらえそうです。が、まずは起業を紹介した本や雑誌記事。これらは成功例がほとんどです。実際には起業して成功した例の何倍もの失敗例があるわけです。成功したから雑誌などに紹介されるわけです。失敗した大多数の例のほうが参考になるはずなのですが、それらはなかなか紹介されない。で、成功例を読んで起業を夢見て挫折や失敗するということになる。また開業の届け出などの手順書もあります。これも図書館の蔵書では古かったりします。開業手順が書かれた本の1-2冊程度なら、自分で最新の情報を書店で購入することをお勧めします。また開業方法は業種によって様々だとは思いますが、本で勉強するほど難しいものではないことも多くて、私の場合は税務署に開業届を出して、銀行で事業用の口座を作って、それだけでした。重要なのは起業後に事業を継続させることなわけで、これは自分で悩んで考えて苦しむしかない。成功例の本は、そのかたの条件で成功した例なので、アナタとそのかたは別人。条件は全く違うでしょうから、そのまま同じことはできない。ただし読んで自分の励みにするという読み方なら本を読む意味もあるとは思います。
ビジネス支援図書館という幻想
図書館でのビジネス支援がなかなか盛んにならない現実があるわけですが、上の項で書いたように「図書館の持つ冊子情報源やデータベース等」は、実際の仕事に必要な情報ニーズには応えられない場合が多い。だから「図書館の持つ冊子情報源やデータベース等活用すれば、市民の起業とNPOや SOHOを含むマイクロビジネス等の創業を喚起し、また、地域経済の担い手である中小企業やベンチャービジネスの支援を行うことが可能となります」というのは幻想です、残念ながら。
上の項に様々な例は特殊な例をわざと挙げたわけではなくて、普通に調査すれば図書館で入手できない情報がいかに多いことか実感できます。だから図書館のかたが普段から利用者のかたからレファレンス(参考調査)を受けていれば、「図書館の持つ冊子情報源やデータベース等活用」して起業や創業を支援するというのは、なかなか難しいということが分かるはずなのです。
とはいうもののビジネス情報について、図書館が役に立たないわけではないはずです。ビジネス情報に限らず、普段から目の前にある調査にキチンと取り組んでいれば、ビジネス情報についても、それ以外の情報についても様々に仕事がブラッシュアップされていくはずです。データベース検索の高度な勉強をしたり、マーケティングの勉強をしたりするのも良いですが、毎日の仕事に取り組んで、その中から問題を見つけて解決しようと努力するのは図書館に限らずどんな仕事でも大事でしょう。
例えばコラム258号で「書籍全文検索の利点、不利点」について書きました。図書館でレファレンス業務を行っていれば、書籍の全文検索が可能なら良いのにと思うことは多いはずです。ならば書籍の電子化を積極的に進めるにはどうしたら良いか考える。それが結果として、ビジネス情報も含めた情報全般の入手の向上につながる。そして例えば国会図書館まで行かなくても、蕎麦の打ち方について本や文献を網羅的に調査するというニーズにも応えられるようになるでしょう。
簡単に言えば、夢を見るのではなく現実を見る。仕事に必要な情報入手を支援するというのは、そこから始まると思います。
ずいぶんなエラソーを書きましたが私自身、公共の特許情報室で地域の企業に特許情報や産業情報の提供をするという構想が実情に合わなくて挫折した経験者です。
情報室自体は、特許情報が紙(冊子体)からCD、そしてオンラインのデータに移行していくにつれて情報室の存在意味が無くなり、消滅しました。その情報室の職員だった私ですが、企業のかたは特許情報の入手方法の案内が必要なのではなくて、自分に必要な特許情報そのものが欲しいというニーズが分かったことから、特許調査の事務所を開業して今に至ります。
2000年代前半に始まったビジネス支援図書館が今だに同じ状況で足踏みして存続しているのを見ると、時代の流れに沿って消滅した特許情報室は幸いだったように思います。