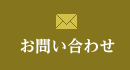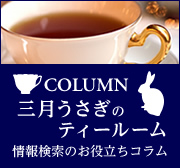情報検索コラム
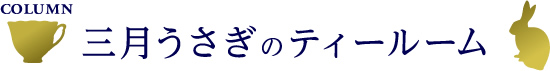
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
J-STAGE での無効資料調査(非特許文献) 2:指定検索の不利点
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
J-STAGE を使った無効資料調査の2回目です。今回は J-STAGE の「詳細検索」のページ(https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja)を開くと表示される「指定検索」について書きます。
「指定検索」の画面は簡単に検索できるのですが、残念ながら無効資料調査での検索には向きません。今回は「指定検索」を無効資料調査での検索に使う場合の不利点を説明しました。
「詳細検索」のページは「指定検索」が基本で表示されるため、「指定検索」で検索しようとするかたが多いと思われます。「指定検索」で上手く検索できなくて悩む、または J-STAGE は無効資料調査に使えないと早々に見限ってしまうかたもいらっしゃるようです。ということで、まずは「指定検索」の不利点を説明しました。
予め書いておくと、J-STAGE で無効資料調査を行う場合は「指定検索」ではなく「検索式を入力」を使用することが好ましいと思います。「検索式を入力」の使い方などは改めて説明する予定です。
【参考:J-STAGE を使った無効資料調査について】
特許の無効資料調査は特許文献を調査することが主流ですが、非特許文献の調査も行う場合があります。非特許文献として論文や雑誌記事のデータベース検索を行う場合、JDreamⅢなどの商用データベースを使う方法があります。しかしながら商用データベーは高価な場合もあり、さらに現在では
Google Scholar などの無料で論文検索が可能なシステムがあるため、商用データベースの導入をしていないかたも多いのではないかと思われます。
当事務所でも以前は JDreamⅢ を利用していましたが、数年前に JDreamⅢ の契約を解除しました。そんな中で先日、無効資料調査で非特許文献の調査依頼を頂きました。特に
J-STAGE を使って調査してほしいとのことでした。J-STAGE で無効資料調査を行うのは初めてでしたが、結論から言うと次の2点となりました。
・J-STAGE は無効資料調査に使える面が大きい。
・かなりクセが強く、使いこなしにコツが必要。
というわけで、J-STAGE を無効資料調査に使う場合のコツや注意点を紹介したいと思います。
【用語の説明】
無効資料調査:特定の特許権を無効にする資料を探す調査。
特許出願が特許庁での審査に通って特許権が設定されると、その特許権に含まれる技術を他社が使いたい場合は特許権者にロイヤリティを支払う必要が生じる。よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰すために無効審判を請求する。その際に、特許が無効であることを証明する文献(証拠)が必要となる。この証拠文献が「無効資料」である。無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」として採用される。無効にできる資料であれば特許文献でも非特許文献でも良い。
非特許文献:
特許文献以外の文献。論文や雑誌記事などの他、書籍や新聞記事、カタログや説明書など特許文献以外の公知文献全てが対象。
【参考:前回までのコラム】
コラム267号(2025/08/05UP)J-STAGE での無効資料調査(非特許文献) 1:J-STAGEの概要
※ J-STAGE はリンクフリーではないため、文中および「※参考URL」の項へURLを記載しています。
※このコラムの内容は2025年9月9日時点での内容です。検索システムは変更されている場合もあります。
「指定検索」は特許調査に向かない
J-STAGE の日本語トップページ(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja)の検索ボックスの右下にある「検索条件の詳細設定」をクリックすると「詳細検索」のページ(https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja)が表示されます。
基本の表示はプルダウンメニューと検索ボックスを使う「指定検索」ですが、無効資料調査を行うのであれば右側に表示される「検索式を入力」をクリックして、検索式入力方式を使うことをお勧めします。「指定検索」をお勧めしない主な理由は次の2点です。
・「指定検索」の不利点1:検索ボックス内はAND演算される
・「指定検索」の不利点2:指定検索は複雑な検索ができない
この2点を詳しく説明したいと思います。
※以下は「ヘルプ」ページ(https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/ToolsOfSearchArticlesPage/-char/ja)も参照しながら読んで頂くと理解しやすいと思います。
「指定検索」の不利点1:検索ボックス内はAND演算される
「指定検索」が特許検索に向かない理由のひとつとして、検索ボックス一行内はAND演算に固定されている点です。特許調査として特に無効資料調査でのキーワード検索では同義語や異表記を広くOR演算して検索することが多いと思います。例えば「数値の検知」に関する検索を広く行う場合に「センサー センシング 検知 検出 計測 測定 認識」などを全てOR演算して、これら全てと「数値」をAND演算したいとします。これを「指定検索」で行う場合は例えば「センサー」「センシング」「検知」などひとつずつワードを一行の検索ボックスに入力して、上下関係をプルダウンメニューから「OR」で指定してから最後の行に「数値」を入力して、上下関係をプルダウンメニューから「AND」を指定する形式です。この方法で「(センサー OR センシング OR 検知) AND 数値」の検索ができます。
一般的に商用(有料)の検索システムでは一行に入力した複数のキーワードの関係をANDなのか、ORなのか、または近傍検索するのかなどが指定できる場合が多いです。でも無料の検索システムでは一行に入力した複数のキーワードの関係が固定されている場合があります。例えば皆さんが使う機会が多いと思われる無料の検索システム 特許情報プラットフォーム J-Platpat の「特許・実用新案検索」では一行の検索ボックス内はOR演算または近傍検索です。特許の検索として一行の検索ボックス内の検索方式が固定される場合はOR演算されるかたちのほうが好ましいのですが、 J-STAGE の「指定検索」は特許検索に適したシステム設計ではなく、一般のかたが論文検索するのに適した設計となっているのだと思われます。
「指定検索」の不利点2:指定検索は複雑な検索ができない
OR演算を一行ずつ入力するのも手間ですが、さらに不都合なことに検索ボックスの行の追加は最大で4行までです。ということは「センサー センシング 検知 検出 計測 測定 認識」などを全てOR演算したくても「センサー」「センシング」「検知」「検出」の4つしかOR演算できません。4つOR演算してさらに「計測」「測定」「認識」など入力したくてもできないし、「数値」でAND演算したくてもできません。
さらに4行まで入力可能だからといっても、例えば「(センサー OR センシング) AND (数値 OR データ)の検索をしたくてもできません。1行目「センサー」、2行目OR指定で「センシング」、3行目AND指定で「数値」を入力します。上から順に演算されるので、ここまでで「(センサー OR センシング) AND 数値」の検索が可能です。問題は「(センサー OR センシング)」に「(数値 OR データ)」をAND演算する検索ができないことです。
試しに1行目「センサー」、2行目OR指定で「センシング」、3行目AND指定で「数値」、そして4行目OR指定で「データ」を入力すると・・・私の予想では「((センサー OR センシング) AND 数値) OR データ」で、多数の「データ」がヒットするのではと推測したのですが、4行目はなぜか自動的にAND演算されてしまって「((センサー OR センシング) AND 数値) AND データ」で絞り込まれてしまいました。
非特許文献の検索は多くのキーワードを多様に使って検索式も多様に作りたいのですが、J-STAGE の指定検索ではかなり難しいというよりも、できない。この点で「指定検索」は特許調査には向かないといえると思います。
「指定検索」の特徴:絞り込んだ検索向けの設計である
上に書いた2点の不利点から察すると、「指定検索」はデータを絞り込んで適合率や適合性の高い少数の文献をヒットさせる検索画面および設計になっていると思われます。
例えば学生さんが論文やレポートを書くにあたって関連する文献をいくつか読みたいとか、特定のテーマについての代表的な文献を入手したいとか、自分が詳しくない事柄について説明している文献が欲しいとか、少数の適切な文献をピンポイントでヒットさせるような設計になっている印象です。
特許の無効資料調査の場合は文献を広く拾い出して(再現率重視)、審査での見落としを見つけたいという調査戦略をとる場合も多い。そのような調査戦略の場合は、絞り込んでピンポイントで適合する文献をヒットさせる検索向けの「指定検索」は使いにくいと思います。
初めて使ったかたの失敗例:判断ミスが致命的な失敗例
最初に書いたように「詳細検索」のページを開くと「指定検索」が基本で表示されるため、「指定検索」で検索しようとするかたが多いと思います。「指定検索」は気軽に検索できそうな画面なので、いきなり検索を始めてしまうかたも多いと思います。しかしながら上の2点の不利点など、検索画面を見ただけでは分からない点があります。
実際に J-STAGE を初めて使ったかたで「指定検索」の画面で無効資料調査を行おうとしてこんな検索をしたかたがいます。検索の失敗例として紹介します。以下の【検索1】【検索2】【検索3】のA、B、C、Dはキーワード、Xは数字を表します。なお無効資料調査なので出願日以前発行で調査を行うため、発行年を20XX年以前で指定した検索です。
-----------------------------------------------------------
【検索1】
論文タイトル:A or B で検索するとXX件がヒット。単語は or 検索が可能と判断した。
【検索2】
論文タイトル:A or B AND 論文タイトル:C or D ではヒットゼロ。
論文タイトル という条件が厳しすぎた(狭すぎた)と判断。
【検索3】
全文:A or B AND 全文:C or D この条件でX,XXX件がヒット。
論文タイトルに向く単語、全文に向く単語など、それぞれの単語やフレーズにあわせて条件を変えることが必要。
-----------------------------------------------------------
さて皆さん、このかたはどういう検索をしたと思いますか。
まず【検索1】の「論文タイトル:A or B で検索するとXX件がヒット」とのことです。この検索を確認するために私は次のとおり検索してみました。
1行目のプルダウンメニューは「論文タイトル」でキーワード「A」を入力。
2行目のプルダウンメニューは「論文タイトル」でキーワード「B」を入力。
上下関係をプルダウンメニューから「OR」で指定して、20XX年以前の発行年を指定して検索。すると結果はXX,XXX件。つまり数万件ヒットしました。
キーワードのA、Bとも一般的な用語です。現時点で600万近い記事数が収録されている J-STAGE で論文タイトルを指定したヒット件数としては数万件のヒットは妥当だと思われます。参考として特許情報プラットフォーム J-Platpat で特許文献を同じキーワードA、Bを使ってOR演算して、発明の名称(タイトル)を指定して20XX年以前の発行で検索した場合も数万件ヒットします。「XX件がヒット」ということで、たった数十件のヒット件数というのは、なんだかヘンです。
【検索2】で「論文タイトル:A or B AND 論文タイトル:C or D ではヒットゼロ」という書き方を見て、これはもしかしたら次のように検索したのかもしれないと思って試しました。
1行目のプルダウンメニューは「論文タイトル」で検索ボックスに「A or B」を入力。
2行目のプルダウンメニューは「論文タイトル」で検索ボックスに「C or D」を入力。
上下関係をプルダウンメニューから「AND」で指定して、20XX年以前の発行年を指定して検索。すると結果は確かに0件。
試しに【検索1】も1行目のプルダウンメニューは「論文タイトル」で検索ボックスに「A or B」を入力して検索したところ、確かにXX件がヒットしました・・・。
上の項「「指定検索」の不利点1」で説明したとおり「指定検索」の検索ボックス内はAND演算です。だから「論文タイトル」で検索ボックスに「A or B」を入力して検索した場合に検索システム側では、検索ボックス内はAND演算されます。そして「or」はヘルプのストップワード一覧には載っていませんが、ストップワードの扱いになっているものと思われ、結果として「A AND B」の検索が行われます。試しに「論文タイトル」で検索ボックスに「A B」を入力して検索した場合も同じXX件がヒットしました。皆さんご自分で任意のキーワード2つを使って「A or B」の検索と「A B」の検索をしてみてください。同じ件数になると思います。
この失敗例の検索を行ったかたは特許調査部門で特許調査を担当されているかたです。特許検索には慣れているため、特許文献の基本的な検索として同じ概念ごとにキーワードをOR演算して、それらを掛け合わせて絞り込むという検索を普段から行っているものと思われます。そのため J-STAGE でも同じ感覚で検索したのだと思います。
この失敗例で大事なことは検索ボックスへの入力が不適切だったことよりも、判断が不適切だったということです。【検索1】で「論文タイトル:A or B で検索するとXX件がヒット」についての判断は「単語は or 検索が可能と判断した」ですが、XX件がヒットしたなら本来は「少なすぎる」と判断できないといけない。無効資料調査ならば非特許文献の調査に先立って特許文献の調査も行っているはずで、キーワードの「A」も「B」も非常に一般的な用語、例えば「検出」と「検知」のような同じ概念を表す用語なので、この2つをOR演算してたった数十件のヒットというのは、特許文献の調査結果から考えてもヘンだと思ってほしかったです。
特に【検索2】で「論文タイトル:A or B AND 論文タイトル:C or D ではヒットゼロ」は、正しくこの検索を行ったならあり得ないヒット件数です。例えば論文タイトルを検索して一般的なキーワードで「センサー or センシング」と「数値 or データ」をAND演算してヒット件数がゼロはあり得ない。この検索なら実際には「センシングデータ」とか「センサーから得られた数値」とか普通に考えても論文タイトルに使われそうな言葉は多数考えられます。そのようなタイトル例も予想しながら検索を行うわけで、ゼロというのはおかしいと思ってほしかったところです。でもこのかたは「論文タイトル という条件が厳しすぎた(狭すぎた)」と判断してしまった。次の【検索3】も判断ミスの続きです。この検索例は一見正しい判断をしていそうに見えます。普段あまり文献検索をしないかたは、この失敗例を見ても失敗だとは思わないかもしれません。一見正しい判断をしていそうというのが落し穴だったようです。
【用語の説明】
ストップワード:言葉には「どんな文章にも出てきてしまうような非常に一般的な単語」な単語というのがあります。英語ならば「the」「of」「it」「where」などです。このような一般的な単語を検索に使うと、検索結果としてあまりにも多くのページが該当していまうため、これら一般的な単語は検索するキーワードから自動的に除外されるしくみになっています。この検索から除外される一般的な単語のことを「ストップワード(ストップ語)」といいます。
(引用:拙著『社会人・学生のための情報検索入門』発行/ひつじ書房2009年 p81)
初めて使う検索システムは必ず「ヘルプ」を参照すること:急がば回れ
初めて使う検索システムは、最初に必ず「ヘルプ」を参照しましょう。特に調査部門のかたなどで普段から検索に慣れているかたほど、いきなり検索してしまうものだと思います。特に J-STAGE の指定検索のように画面が簡単だと、つい自分本位に検索して自分本位に判断して自分の間違いに気付かない。すると今回紹介したような失敗が発生します。
自分本位に検索してもヘンだなと判断したなら「ヘルプ」を参照したはずで、自分本位に検索しても判断が適切なら自分の間違いに気付くから失敗せずにすみます。
と書いている私自身も白状すると、じつは最初はヘルプも見ずにいきなり「センサー センシング 検知 検出 計測 測定 認識」などとズラーっと関連語を入力して全てOR演算しようとしました。すると「検索条件と一致する記事が見つかりませんでした。」と赤字で表示されて、あ?と思って(苦笑)ヘルプを参照した次第です。その意味では上で紹介した失敗例の検索をしたかたは微妙にヒットしたのが災いしたかもしれません。
J-STAGE に限らず簡単な検索画面の場合、いきなり検索して失敗する例は多いと思われます。初めて使う検索システムは最初に必ず「ヘルプ」を参照するということを覚えておかれると良いと思います。これを別の言い方でいうなら、急がば回れ、です。
※参考URL一覧
※参考URL1:J-STAGE トップページ(日本語)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
※参考URL2:J-STAGE 詳細検索のページ
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja
※参考URL3:J-STAGE 詳細検索のヘルプページ
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/ToolsOfSearchArticlesPage/-char/ja
お詫びと訂正
前回のコラム267号で J-STAGE は単語単位の検索だと説明しましたが、その後、詳しく確認したところ J-STAGE の全文検索で特に日本語での検索は文字列検索でした。ただし日本語での1文字のみの検索ができないしくみです。詳しくは次回のコラム269号で説明する予定です。
J-STAGE で無効資料調査する場合、「指定検索」はもともと特許調査の検索向きには作られていないこと、ヘルプを参照することが大事であること、この2点を覚えておいていただくといいかなと思います。
なお無料の検索システムの特徴としては、 J-STAGE に限らず検索機能が限られることが多いです。今回のコラムで説明したこと(例:検索ボックス内はOR演算できない)以外にも、無料の検索システムを使いこなすためには利用する側で様々に工夫や勉強をしないといけない面が出てきます。来月以降のコラムもそのような面を含めて、ひとつひとつ丁寧に案内していきたいと思っています。