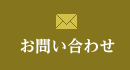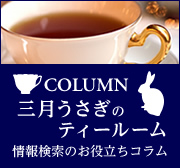情報検索コラム
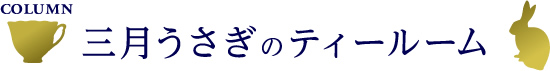
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
J-STAGE での無効資料調査(非特許文献) 1:J-STAGEの概要
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
特許の無効資料調査は特許文献を調査することが主流ではありますが、非特許文献の調査も行う場合があります。非特許文献として論文や雑誌記事のデータベース検索を行う場合、JDreamⅢなどの商用データベースを使う方法があります。しかしながら商用データベーは高価なものもあり、さらに現在では Google Scholar などの無料で論文検索が可能なシステムがあるため、普段から頻繁に使わない場合は商用データベースの導入をしていないかたも多いのではないかと思われます。
当事務所でも以前は JDreamⅢ を利用していました。利用方法としては他のデータベースシステムからゲートウェイで利用する方式で、従量制での利用でした。JDreamⅢ 側の運用として従量制での利用方法ができなくなったこと、また非特許文献の調査は頻繁には行わないことも考慮し、数年前に JDreamⅢ の契約を解除しました。そんな中で先日、無効資料調査で非特許文献の調査依頼を頂きました。特に J-STAGE を使って調査してほしいとのことでした。
J-STAGE で無効資料調査を行うのは初めてでしたが、結論から言うと次の2点となりました。
・J-STAGE は無効資料調査に使える面が大きい。
・かなりクセが強く、使いこなしにコツが必要。
というわけで、J-STAGE を無効資料調査に使う場合のコツや注意点を紹介したいと思います。今回のコラムでは J-STAGE の概要を中心に紹介致します。
【用語の説明】
無効資料調査:特定の特許権を無効にする資料を探す調査。
特許出願が特許庁での審査に通って特許権が設定されると、その特許権に含まれる技術を他社が使いたい場合は特許権者にロイヤリティを支払う必要が生じる。よって、その特許技術を使いたい会社(他社)が特許権を潰すために無効審判を請求する。その際に、特許が無効であることを証明する文献(証拠)が必要となる。この証拠文献が「無効資料」。無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」として採用される。無効にできる資料であれば特許文献でも非特許文献でも良い。
非特許文献:
特許文献以外の文献。論文や雑誌記事などの他、書籍や新聞記事、カタログや説明書など特許文献以外の公知文献全てが対象。
J-STAGE の収録データ量
※ J-STAGE のサイトはリンクフリーではないため、参考URLとして下へ別記します。
※このコラムの記載内容は2025年8月5日時点での内容です。
J-STAGE(※参考URL1) は「J-STAGEの概要」に書かれているとおり「国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営する電子ジャーナルプラットフォーム」です(※参考URL2)。「J-STAGEの沿革」のページ(※参考URL3)を確認すると運用開始が1999年です。私が J-STAGEを知ったのは2003年頃ですが、「J-STAGEの沿革」のページで確認すると当時の公開誌数は「100誌」とのことです。当時、実際に使ってみましたが収録誌が少なくて限られた情報しか検索できないという印象でした。その意味では広く情報収集したい無効資料調査には向かなくて、当時は JDreamⅢ を使っていたこともあり、J-STAGE を利用対象としていませんでいした。
その後も J-STAGE は特定の文献のPDFを読むなどの利用はしていましたが、広く検索することはしていませんでした。なお特許調査では無効資料調査ではなくても、技術理解や情報収集のために論文検索をすることがありますが、その場合は国立情報学研究所の CiNii や Google Scholar 、また国立国会図書館の NDL SEARCH を使っていました。
というわけで J-STAGE で検索することはあまり無かったのですが、今回 J-STAGE を使ってみて最初の感想は収録範囲が飛躍的に拡大しているという点でした。このコラムを書いている時点で収録記事数は5,863,768記事、資料数は4,263資料となっています。検索できる資料(論文誌、雑誌、機関誌、会議資料など)が増えていること、また最近の記事が検索できるだけでなく1930年代や1940年代、1950年代などの古い文献まで遡及してデータ化されて検索できるようになっていました。
少し余談になりますが、1930年代や1940年代などの古い文献が調査に必要なのかと疑問に思うかたもいるかもしれませんが、無効資料調査の場合は分野によっては古い文献が重要な場合もあるのです。例えば機械分野の調査の場合に、機械の要素(ギヤ、軸、ばね、管、弁など)は古い文献が侮れない。例えば英国や米国の古い特許公報に、こんな昔に既にこういう技術思想が記載されていたのかと驚くこともあります。また無効資料調査の場合に時々ある例として、潰したい請求項の構成要件のなかに「当たり前のこと」が含まれていて、他の文献ではわざわざ明文化されていなくて見つからないという構成要件があったりするのです。これは実際の審判などでは容易に想到できると判断されるのではないかと思われるものの、調査段階でのサーチャーの仕事としては明文化されている文献を見つけることが仕事です。このような構成要件が書籍や古い文献には明文化されている場合もあるため、古い文献まで遡及してデータ化されて検索できるようになっているということは大事なのです。
J-STAGE は全文検索が可能
お詫びと訂正:
その後、詳しく確認したところ J-STAGE の全文検索で特に日本語での検索は文字列検索でした。ただし日本語での1文字のみの検索ができないしくみです。詳しくはコラム269号で説明する予定です。
もう一つ大きな特徴としては文献の全文検索が可能だという点です。論文記事の無料検索システムでは書誌事項(タイトル、著者名、雑誌名など)でのに限られる場合がありますが、J-STAGE では文献の全文検索が可能です。その点でも特許の無効資料調査に適しているといえます。特に検索結果からPDFでの全文の確認が迅速に行える点も、大量の文献を調査する特許調査では大事な利点といえます。
ただし、全文検索のしくみが独特です。検索のしくみは次回以降のコラムで詳しく紹介したいと思いますが、 J-STAGE の全文検索は文字列検索ではなく単語単位の検索です。文字列検索と単語単位の検索の違いを簡単に説明します。(参考:拙著『社会人・学生のための情報検索入門』発行/ひつじ書房2009年 p.22-24)
文字列検索:検索語として入力した文字列と、同じ文字列をを持つデータを拾ってくる。
例えば芥川龍之介の「羅生門」の冒頭のテキストがデータ収録されているとします。
「ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。」
このテキストの文字列と同じ文字列が検索語として入力された場合に、このデータがヒットするしくみが文字列検索です。例えば「暮方」「下人」「羅生門」「雨やみ」などの文字列で検索した場合は、「羅生門」の冒頭のテキストデータに一致する文字列があるので、この「羅生門」のテキストデータがヒットします。もっと極端な例を挙げれば「る。一」とか「下で雨や」など意味をなさない文字列を入力しても検索されます。
文字列検索が可能な検索システムは多いです。例えば特許情報プラットフォーム J-Platpat も文字列検索です。この文字列検索は気軽に検索しやすいのですが、難点は少しでも違う表記(文字列)を入力するとヒットしない場合が多い点です。例えば「暮方」ならヒットするけれど「暮れ方」だとヒットしない。また「雨やみ」はヒットするけれど「雨止み」はヒットしないというしくみです。
単語単位の検索:データファイルの文字列を単語単位に分割する。検索語として入力した文字列が、データファイルの単語単位の文字列と一致した場合はヒットする。
同じく芥川龍之介の「羅生門」の冒頭のテキストがデータ収録される場合に、次のように単語単位に分割されたとします。
「/ある日 / の / 暮方 / の / 事 / である / 。 / 一人 / の / 下人 / が / 、 / 羅生門 / の / 下 /
で / 雨やみ / を / 待って / いた / 。/」
この場合も「暮方」「下人」「羅生門」「雨やみ」などの文字列で検索した場合は当然ながらこの「羅生門」のテキストデータがヒットします。さらにシステムにもよりますが、「暮れ方」で「暮方」、「雨止み」で「雨やみ」がヒットするなど、同義語や異表記での検索に対応している場合があります。
収録されたテキストデータが単語単位に分割される代表的な例が Google の検索システムです。上に書いたとおり J-STAGE の全文検索は文字列検索ではなく単語単位の検索なので、Google と同じように検索できるかというと、これがかなりクセが強くて Google とは似ているようでかなり違う。大雑把にいえば、収録されたテキストデータが単語単位に分割されたうえで広く検索されて、関連度が高い順に表示されるという点では Google に似ているのですが、Google検索と同じ感覚では検索できません。かといって当然ながら文字列検索とも違う。特に無効資料調査では、どのように検索したかを厳しく問われますので、検索のしくみを十分に理解して検索する必要があります。
というわけで、次回以降に J-STAGE での検索について詳しく紹介したいと思います。
※参考URL一覧
※参考URL1:J-STAGE(日本語のトップページ)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
※参考URL2:J-STAGEの概要
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageOverview/-char/ja
※参考URL3:J-STAGEの沿革
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageHistory/-char/ja
コラムのなかで英国や米国の1930年代や1940年代の古い特許公報を見て、こんな昔に既にこういう技術思想が記載されていたのかと思うと書きました。これについてさらに言うなら同時代の日本の特許公報を見ると、この時代の日本は英国や米国に比べた場合に残念ながら技術的には後進国だったのだなと感じます。もちろんなかには日本でも高度な発明もあったと思われるし、様々な条件も考慮すると簡単に比較できるものではないとは思います。でも特許公報を読みながら単純に比較すると欧米のほうが技術力は高かったことが実感できる場合が多いです。ということは、あの時代に日本は自国よりも技術力の高い他国と戦争していたのだなと思うわけで、特許調査をしていると技術面から歴史の片鱗が見えることもあります。今月は8月ということで戦争を振り返る時期でもあり、サーチャーの視点で感じることを少しだけ書いてみました。