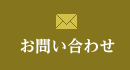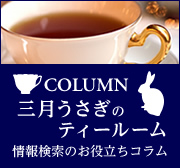情報検索コラム
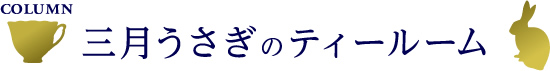
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
無効資料調査における日付 -非特許情報の公知日-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
今回は特許の無効資料調査で非特許文献を調査するときの「日付」について書きます。
検索の話しに入る前に、無効資料調査について大まかに説明します
なお前回のコラムでも以下と同様の説明をしました。
前回のコラムと説明内容が重複しますので、既にご存知の方は読み飛ばして頂いて構いません。
特許調査には出願前の先行例調査や技術動向調査、侵害防止調査、無効資料調査など、
調査の目的によって様々な調査があります。
その中でも特に無効資料調査においては「日付」が大事なポイントのひとつです。
無効資料調査は特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。
特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。
この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。
これも大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。
ここで出てくる日付が「出願日以前に公知」。無効資料調査を行う際は、この日付が大事です。
さて、ここまで理解したところで今回のテーマ「非特許情報の公知日」です。
「非特許情報(非特許文献)」は特許業界の専門用語で、一般には馴染みにくい用語かと思います。
簡単に言えば論文や雑誌記事、また新聞記事や書籍、灰色文献やインターネット情報など、
特許文献以外の文献および情報全てを指す用語です。
特許調査では特許情報(特許文献)の調査を行うのがメイン(主)です。
で、このメインの特許情報以外の情報を全てまとめて称する用語が「非特許情報」です。
論文、雑誌記事、新聞記事、書籍、パンフレット、会議資料、ウェブページなどと個別に言わなくても、
全部まとめて「非特許情報(非特許文献)」の一言で通じるようになっています。
非特許情報も無効資料として使えますが、「出願日以前に公知」が大事であるとに変わりはありません。
非特許情報は多岐に渡るうえ、公知日(発行日)も様々に記載されます。
それらの中で皆さんの参考になりそうな点を、いくつかご紹介したいと思います。
論文、雑誌記事、技報などの発行物 ※追記有り
非特許文献の場合「公知日」が厳しく意識されていません。
特許文献の場合は上に書いたとおり、出願日や公知日が審査や権利に大きく影響するので、
非常に厳密に記載されています。
でも非特許文献は発行の際、特許制度を意識しないのが普通です。
論文誌や商業雑誌、また技報や白書、会議資料などの発行物には奥付等に「発行日」が印刷されています。
この発行日が公知日として有効だろうと思うのですが、例えば商業誌の場合、発売日は発行日と相違します。
例えば「2010年6月1日発行」と印刷されていても、実際の発売日は「2010年6月15日」だったりする。
さらに「2010年6月1日発行」と印刷されていて実際の発売日は「2010年5月1日」だったりする。
このような実際の発売日に対する「未来の日付」が発行日として印刷されている場合も珍しくありません。
だから奥付に印刷された日付では「この日に公知だった」と確実に証明できない。
この場合、例えば該当する雑誌を所蔵している図書館の「受入れ印の日付」で証明するのが確実です。
細かいハナシですが、論文誌や雑誌は図書館に届いて即日、遅くとも翌日に配架される場合が多いのです。
要するに雑誌類は速報性が大事で、利用者の皆さんも発行日(発売日)を熟知しています。
よって受入日が公知日として、そんなに日が違わない場合が多いのです。
とはいうものの、
じつは近年、受入印を廃止する図書館も多くなってきました。
また電子雑誌が主流になってきていいることもあり、日付は「発行日」しか分からない場合も多いのです。
無効資料調査は古い文献を入手する場合が多いので受入印あるはず、と思っていても
古い文献が電子化された場合、受入印のページは電子化されない場合もあります。
ということをふまえたうえで、雑誌等の文献検索の際は日付をややゆるく検索します。
例えば無効にしたい公報の出願日が「2012年3月4日」の場合、「2012年4月30日以前」くらいで検索します。
特に非特許文献の検索システム場合は日付はあまり重要視されていない場合が多いので、
「〇年〇月」と月単位での検索や、「〇年」と年単位での検索しかできない場合もあります。
よって必然的に、ゆるく検索せざるを得ない面もあります。
そのうえで、無効資料として使えそうな文献があった場合、発行日を確認します。
発行日が無効にしたい特許公報の出願日以前であることが確実ならば(例えば数か月以上前)、
発行日の記載されている箇所を複写等で入手します。
発行日の記載されている箇所は、論文誌や会議資料、白書などは奥付に記載されていますので「奥付」。
商業雑誌の場合は奥付が無いことが多いです。
奥付が無い場合は裏表紙の端に発行日が印刷されている場合が多いので「裏表紙」。
そして、この発行日の号に確かに掲載されていたことの証明として、
雑誌名と〇年〇月号という箇所と献タイトルを含めた「目次」も必要です。
さて、無効にしたい特許公報の出願日前後1か月くらいの発行日の場合です。
特に発行日の日付は出願日より少し後だけれど、もしかしたら出願日以前に公知だった可能性がある場合。
これを食い下がって(!)無効資料に使うなら、
やはり今のところは図書館等の受入れ印の日付で証明するしかないと思います。
受入印等で証明できない場合は、たぶん他の方法は無いと思うので、あきらめるしかないかもしれません。
たぶん他のサーチャーのかたも、ほぼ同様の方法を行っているのではないかと思いますが、いかがでしょう。
※追記(2020年6月23日):
このコラムを2020年6月9日にUPした後で、
非特許文献の公知日の判断について特許庁へ直接問い合わせしました。
以下カギカッコ内「 」は特許庁から頂いた回答からの抜粋、丸カッコ内( )は味岡の注です。
回答は「公知日は、実際に公知になった日付であり、公知日が不明な場合又は確認が困難な場合も同様」
とのことなので、重要なのは「実際に公知になった日付」です。
さらに「発行日との記載があれば、通常はその日に発行されたものと考えられますが、
実際に公知となった日とずれている場合には、実際に公知となった日(注:図書館での受入日等)が公知日」
とのことです。
つまり通常は発行日に発行されているとするけれど、発行日が実際に公知となった日とずれている場合には
図書館での受入日の印があれば、その日が公知日となるという回答だと理解して良いでしょう。
さらに「いずれにしましても刊行物に応じて異なるものとなります」ということで、
「一概にどれが公知日であることをお答えすることは、いたしかねます」との回答でした。
というわけなので、公知日を意識して発行していない非特許文献については、
実際の公知日を証明可能な情報として、できれば図書館での受入日等を入手するのが良いようです。
確実な公知日(受入日等)が入手不可の場合は発行日を入手する、という結論になるかと思います。
よって特許庁へ問い合わせた結果、コラムに書いたこととほぼ同じ結論になりました。
(この回答は、特許庁審判課審判企画室から頂きました。ご多忙中のご対応に感謝致します。)
--------------------------------------以上、6月23日追記--------------------------------------
書籍の奥付:「版」と「刷」の日付に注意
無効資料としての非特許文献が書籍の場合、
じつは奥付に記載される「発行日」は発売日と一致しないことが多いです。
例えば発売日よりも一か月程度未来の日付が記載されたりします。
よって書籍も日付を1か月程度広く検索および調査したほうが良いと思います。
そのうえで、無効資料として使えそうな箇所があった場合、論文誌や雑誌等と同様に発行日を確認します。
無効にしたい特許公報の出願日よりも、かなり以前の発行日なら良いのですが、
無効にしたい特許公報の出願日前後1か月くらいの発行日の場合、
図書館の受入印の日付ページを入手しても、たぶんあまり良い結果は得られない場合が多いかと思います。。
じつは書籍の場合は、受入日が発売日よりも数週間から1-2か月程度遅くなることが多いです。
このタイムラグは発注や装備の手間の都合によるものです。
よって書籍の場合、受入印の日付は使えない場合もあると思っていたほうが良いです。
さて、
この発行日が無効にしたい特許公報の出願日より確実に以前の日付なら奥付ページの複写等を行います。
ただし、書籍の場合は「版」と「刷」の日付に注意が必要です。
書籍の奥付の発行日を見ると、例えばこんなふうに記載されていると思います。
2010年6月1日 初 版第1刷発行
2011年6月1日 第2版第1刷発行
2012年6月1日 第2版第2刷発行
さて無効にしたい特許公報の出願日が 2012年3月4日 の場合、この奥付の日付は有効でしょうか。
図書館情報学での基本に沿って「版」と「刷」の説明をすると、
「版」は、その内容で書籍の版組みをしたということで、その最初の版が「初版」または「第1版」です。
「刷」はその版組みで印刷しただけなので、
「刷」の日付が新しくても内容は「版」の日付での内容のままです。
よって上の日付例を図書館での基本に沿って判断するなら
第2版第1刷発行の「2011年6月1日」に公知になっているはずで、
「2012年3月4日以前」が証明できそうに思います。
ところが、この図書館での基本は特許の無効資料では通用しないんですね。
「2012年6月1日 第2版第2刷発行」←この最も新しい日付が重要視されます。
この日付は「2012年3月4日」よりも後なので不可です。
だから「2011年6月1日第2版第1刷発行」の奥付の本、
またはさらに遡って「2010年6月1日」の初版の本を探して、
同じ記載があることを確認して、その奥付の日付とともに無効資料とする必要があります。
特許調査の世界に入って初めてこの無効資料における「版」と「刷り」の話しを聞いたとき、
新しい技術情報を必要とする図書館利用者と、古い技術情報を必要とする特許調査の違いを感じました。
というか、"特許の審判官をやってるひとって性格がひねくれてるんじゃないの?"(失礼!)
とか思ってしまいましたが、もちろんそんなハナシではありません (^^;
増刷した際に、最初の版から変更された箇所が100%無いかどいうかは分からないと言われてしまう。
特許の無効資料では確実に納得できる情報が求められます。
というわけで、書籍の場合は「刷」の日付で出願日以前のものを入手します。ご注意ください。
新聞記事は発行日と公知日が一致する
非特許情報の中でも発行日と公知日が確実に一致するのが新聞記事です。
よって製品情報やサービス情報など、新聞記事を検索、調査することも有効な調査手段です。
例えば日付が明記されない「製品パンフレット」の日付を証明するために、新聞記事の製品情報を探す。
また「確か○年〇月頃、某地方紙で新システム開始の記事を見た」とのお話しから、
その新システム開始の記事を探す。という調査を行ったりします。
これでもしも見つかった場合、発行日=公知日なので、
新聞記事の日付を含めて複写またはダウンロードすればOKです。
ただし私の今までの経験上、新聞記事で無効資料として有効な情報が見つかった経験はゼロです。
可能性としてはゼロではないと思いますが、無効審判で新聞記事が引用されている例はあまり見たことがありません。
というわけで新聞記事は日付という観点からは公知日が証明しやすい情報であり、
データベースも充実していて、検索及び情報入手しやすい情報なのですが、
無効資料調査としては、補助的に使う面が大きいのではないかと思われます。
以前、このコラムを読んでくださっているかたから
「非特許文献」という用語への違和感をご指摘を頂いたことがあります。
特許業界以外のかたから見ると、論文や雑誌記事、各種資料のほうが「普通の文献」で、
特許公報は特殊な文献である、とのご指摘でした。
本来の論文などがあってこその特許公報のはずだとのことで、
確かに自分たちの書いた論文を「非特許」と書かれると、やや違和感があるかもしれないと思いました。
とはいうものの今回のコラムに書いたとおり、特許調査では特許文献の調査がメインです。
また特許文献以外の情報を全部個別に羅列するのは不可能な面もあります。
というわけで申し訳ないのですが、このコラムでは「非特許情報」「非特許文献」という用語を
これからも使っていきたいと思います。ご理解頂ければと思います。